【ゆきラボ】点数の話、順位の話、評価の話。
こんにちは!えー……もう8月なんですね。夏休みに突入した我が家ですが、実質休みなのは子どもたちだけ。私は8月下旬から休暇を取る予定なので、それまでに片付けたい仕事の山と向き合っているところです。この山がまあ、一向に減らないんですが。
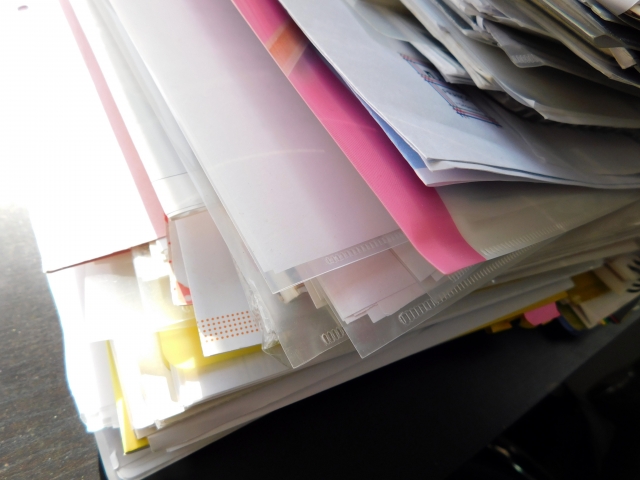
イメージ https://www.photo-ac.com/
夏休みなので、子どもたちはそれぞれ成績表を持ち帰ってきています。ドイツの成績表は、一般的に1~6の数字で点数がつくか、seht gut(非常に良い)からungenügend(不十分)までの6段階で評価がされます。1=sehr gutで、数字が小さいほど高評価になるのが日本の成績のつけかたとは逆ですね。ドイツで「成績表は1ばっかり」というお子さんがいたら、その子、超優秀な子です。
ちょっと紛らわしいのは、ドイツ社会には学校の成績と同様に1~6の数字で製品やサービスの評価をするところもあれば、星の数で評価をつけるところも、10点満点あるいは100点満点で採点するところもあります。何段階評価なのか、数字が大きいほうがいいのか、小さい方がいいのかで評価が全く逆になってしまうので、どの採点方式なのかきちんと確認することが必要です。
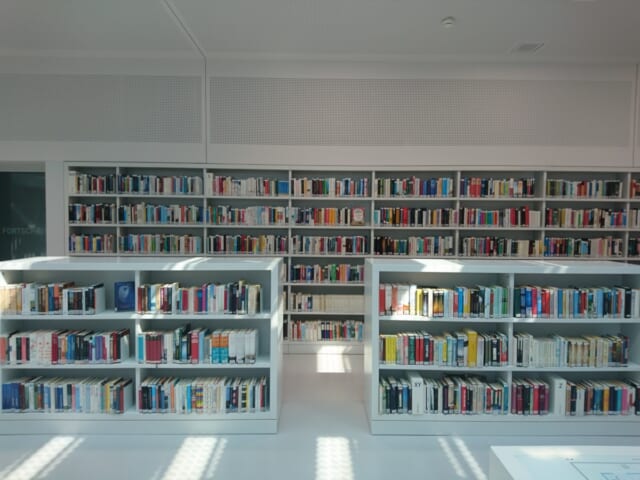
夏休みに入る少し前のことですが、友人のお子さんの通う学校での話です。夏休みに読むのにおすすめしたい本をプレゼンし合うという課題がありました。生徒たちには小さな用紙が配られ、お互いのプレゼンに対する短いコメントを書き込んでいきます。
他人のプレゼンをどう思ったか言葉にするって、それなりに語彙がないと難しいことです。「面白かった」「分かりやすかった」くらいしか思いつくことがなくて、なかなかペンが進まない子も多かったらしいのですが、生徒の1人が「先生、点数を書いてもいいですか?」と提案してきました。10点満点で何点かとか、星がいくつかとか、そういう形式で評価してもいいか、ということです。
短くてもいいから、必ず言葉でコメントをつけるようにという条件つきで点数化をOKしたところ、急にクラスのみんなが張り切りだして、誰のプレゼンに何点をつけるか、一番は誰か…ということで、最初の先生の予定とは違う方向でプレゼン大会が多いに盛り上がってしまった、とのこと。どう感じたのかを言葉で書き表すのは難しくても、点数で良し悪しをジャッジするなら簡単だと思った子も多かったのかもしれません。

イメージ https://www.photo-ac.com/
「一番好きなスイーツは?」とか、「今まで行った旅行先トップ3は?」みたいな他愛のない点数付けや順位付けは、スモールトークの一つとして私たち大人もよく話題にします。世の中のありとあらゆるジャンルのものが、点数や順位をつけて並べられていますし、買い物をするとき(特にオンラインで)それがどのように評価されているかをチェックするのは、私たちにとってとても日常的な営みです。
子どもたちが小さい頃に読んでいた図鑑にも「速い鉄道ランキング」「強い肉食恐竜ランキング」などのページがありました。私自身、子どものころのマンガのキャラクター人気投票に始まって、音楽、ドラマ、アイドルなど様々なランキングがあふれる中で育った記憶があります。人間はそもそも数字や順位をつけるのが好きな生き物なんでしょうか。それとも、大人の社会が数値化と序列にあふれているから、それを反映しているんでしょうか。何より子どもたち自身が、日頃から点数による評価の対象になっているから、他のものを数値で評価することも当たり前のことだと感じてしまっているのかもしれません。
後半も点数や順位の話、続きます。
(残り 1672文字/全文: 3172文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。
会員の方は、ログインしてください。







外部サービスアカウントでログイン
Twitterログイン機能終了のお知らせ
Facebookログイン機能終了のお知らせ