【育成論】自主性という言葉が独り歩きした結果、勝手気ままな子供が増えてきている?
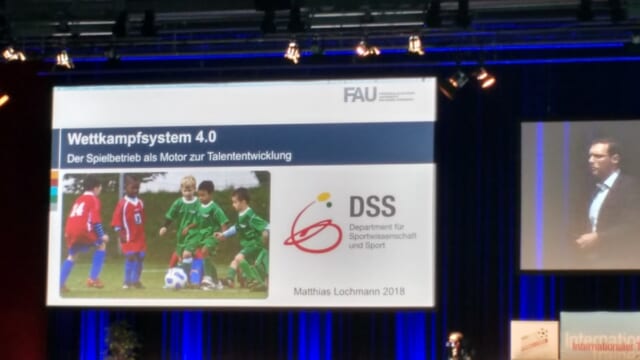
▼ 子どもたちに伝えるべき《自主性》って何?
「《自主的》というよりも《勝手気まま》になってしまっている」
先日、池上正さんと「子どもたちの自主性を大事に守りながら、サッカーのセオリーを身につけるためのヒント」というテーマでWEB対談を行ったが、その中で池上さんが口にしていた言葉だ。
どうも《自主性》という言葉が独り歩きしている気がしてならない。
日本の教育現場、社会環境だと、子供たちがなかなか自分でものを考えて、自分から行動をするという姿勢が育まれにくいという指摘はだいぶされるようになってきた。ただ、自主的にというスタイルにだけ注目が集まり、《何を》《いつ》《どのくらい》《どのように》《なんで》取り組むのか、というのがフワフワしたままのアプローチになっていないだろうか?
冒頭の池上さんの言葉もそこからきている。とある中学校のサッカートレーニングで指導者から練習内容を提示されたが、子供たちが点でバラバラに、自分のやりたいようにだけやってしまう。
「こういうところを改善するために、こうした取り組みが必要だと思うんだ」というメッセージを添えても、やろうとしない。
これも自主的な取り組みだろうか?僕にはそうは思えない。むしろ、創意工夫がないことの表れでしかないのでは?
自分から答えを探そうとする経験があまりないから起こる現象ではないかと思うのだ。現状を正しく把握し、どんな改善方法があるかを模索し、それに精力的にトライするという機会が少ないからかもしれない。
いまも勉強でできるとされる子は模範解答ありきになっていないだろうか?記述問題や質問を自分で作るとなると固まってしまわないだろうか?
(残り 3032文字/全文: 3723文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。
会員の方は、ログインしてください。





外部サービスアカウントでログイン
Twitterログイン機能終了のお知らせ
Facebookログイン機能終了のお知らせ