【ゆきラボ】14歳のハローワーク。長男、初めての“仕事探し”
こんにちは!秋休み明けのゆきラボです。1週間の秋休み……といっても休みなのは子どもだけで、私たち親は平日日中は普通に仕事をしていたのですが、それでも祝日を利用して近くに小旅行に行ったり、普段なかなか手の回らない家の中の片付けをしたりして、少しだけゆっくり過ごしました。
今日お届けするのは、その秋休みの少し前のことです。現在14歳、9年生(中3)の長男は、先日学校の課外授業でフライブルクのジョブセンターに行ってきました。日本でいうところのハローワークで、求職者と事業者をマッチングしたり、就職・転職のためのサポートを行っている公的機関です。

こちらがフライブルクのジョブセンター。私はドイツに来てから今までずっと友人や知人のツテで仕事をしてきたので、この中に入って職探しをした経験がありません。お恥ずかしい話ですが、実は日本での就活やハローワーク通いも経験していません。息子の話によると、求人票が貼られている部屋、キャリア形成や資格取得など職に関する本を大量に集めた図書室、検索用のパソコンがずらりと並ぶ部屋、などがあるのだそうです。見たことがないので想像ですが、たぶん先進国なら、どこの国の職業安定所もおおよそこんな感じなのではないでしょうか。フライブルクの場合、難民・避難民の就業支援もここで行っています。
長男たちはまず施設の使い方のレクチャーを受け、実際に自分が興味のある仕事を探してみたり、その仕事で得られる収入や、必要な資格や最終学歴についてリサーチをしたりして過ごしました。2時間ほどの課外授業でしたが、紙の求人票もオンラインの求人情報も山のようにある中から、自分に合う仕事を見つけて就職するって大変!というのを少し実感できたようです。
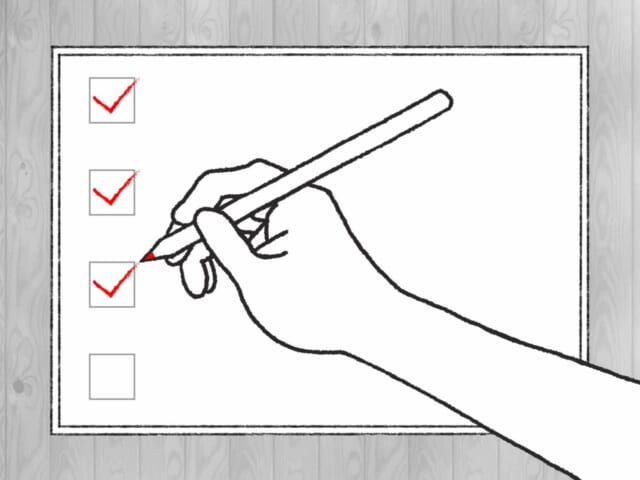
それとは別に、学校で職業適性診断も受けました。この後、履歴書の書き方や面接の受け方、電話のかけ方からメールの書き方まで学校で一通り教わることになっています。なぜこんな課外授業やトレーニングが必要なのかというと、学校で1週間~2週間の職業体験“プラクティクム(Praktikum)”が必修になっているからです。
学校によってプラクティクムを実施する学年や期間は多少異なるようですが、長男の通う学校では、社会福祉や公共サービスの分野で1~2週間プラクティクムを受けるのが必修で、高齢者や障がい者の介護施設、幼稚園や保育園、病院などが対象になります。希望すれば、それ以外の自分の興味のある分野でも、さらにもう1回プラクティクムを受けることが可能です。
(残り 2082文字/全文: 3126文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。
会員の方は、ログインしてください。





外部サービスアカウントでログイン
Twitterログイン機能終了のお知らせ
Facebookログイン機能終了のお知らせ