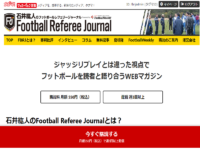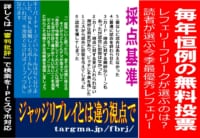無料:山本雄大VARと聳城巧AVARのポイントとプライオリティが整理されたVOR(ビデオオペレーションルーム)内でのcheckとRO(リプレイオペレーター)の精度【レフェリーブリーフィング4.3⑧】
4月3日、日本サッカー協会(JFA)審判委員会が今年第二回目となる『レフェリーブリーフィング』を開催した。
扇谷健司JFA審判委員会委員長の簡単な挨拶の後で、佐藤隆治Jリーグ統括マネジャーが交換プログラムで学んだレフェリングを解説し、その後でJリーグで起きた事象について説明を行った。
湘南ベルマーレ×浦和レッズ戦の23分のケース
VAR「APP Start.PossibleOffSide」
<ゴールネットを揺らす>
VAR「Checking.Checking」
佐藤マネジャー「VARはこの時点でタイトだということが分かっているので、すぐに重要になるPoint of Contactを2つのカメラを使って、どこに当たっているのか正確に確認しにいきます。
Point of Contactが確定したら16mカメラで「DFの左の肩」と間髪入れずに3Dラインの箇所を指定して、一画面でRO(リプレイオペレーター)がラインを引きます。
たった1分という短い時間で、オンサイドと確定させました。あとは証拠映像が必要なので、confirmの映像とします。中継で流すかどうかは中継チーム次第です。
昨年末の『レフェリーブリーフィング』でAccuracyとSPEEDの話をさせて頂きました。
3Dラインは(生成にも)時間がかかるので、2分、120秒はSPEEDの許容範囲として下さいとお願いしました。
でも、このタイトなオフサイドかどうかをVARは1分30秒、90秒でジャッジしました。
要因として一番大きいのは、VARが『どこの』『何を』チェックして、『次に何の作業を』という流れが頭の中で整理されていて、流れるように「Point of contact」「16mカメラ」「DFの左肩」というワードが出ていました。
“えーっと”とか無駄な時間がなかったですよね。
そして、ROが間髪入れずに対応する。この精度が上がっているのが大きい。
もう一つは、昨年までは3Dのラインを引く時に、2画面で引いていました。メリットとして奥行の確認出来るから。
今年は開幕前研修で「一画面でやるよ」と指導しました。海外もほとんど一画面なんですよね。
一画面でやるデメリットは『奥行き』を間違えて、実は後ろ側の選手にラインをひかなければいけなかった、と。そういったミスが起こる可能性もあるので、そこは慎重にやりなさいと指導しています。反面、一画面になったことで多少時間は短縮されました。
が、それ以上にVAR、AVR、ROの自分たちの任務が非常に洗練されてきた一つの事例でした。
一分半でAccuracyとSPEEDは非常にストレスは少なくなったのではないでしょうか。これ以上早さを求められるとなると、Semi-Automated Offside Technology(SAOT:半自動オフサイドテクノロジー)を導入して頂くしかないと思います。」