書評家つじーの「サッカーファンのための読書案内」第5回 鳥飼玖美子・著『通訳者と戦後日米外交』(みすず書房)
宇都宮徹壱ウェブマガジン読者の皆様、こんにちは!つじーです。『書評家つじーの「サッカーファンのための読書案内」』も第5回になります。
「クラシック音楽」をテーマにした第4回の書評はいかがでしたでしょうか。今からでも是非『怖いクラシック』を手に取ってみてください。
今回の選書テーマは「通訳」です。お楽しみください!
通訳は何を伝えるのが役割なのか?
2024年上半期は水原一平さんの一件で「通訳」(以下、通訳者)という職業がスキャンダラスに語られてしまった。これをひとつのスキャンダルとして消化するのではなく、今一度通訳者の役割を考える機会にしてはどうだろう。
昨年、J1リーグ最終節の北海道コンサドーレ札幌vs浦和レッズで通訳者の役割について、今一度考える大きなきっかけに僕は遭遇した。
札幌のシーズン終了セレモニーで、三上代表取締役GMの挨拶中に小野伸二選手の引退セレモニー待ちの浦和サポと思わしき人物から、何かしらの野次等が飛んだ。それを見たミハイロ・ペトロヴィッチ(ミシャ)監督は、その後のスピーチの冒頭で浦和サポを揶揄、または挑発するような発言を連発した。
自分たちのセレモニーを野次等でさえぎられる格好となった、札幌サポは溜飲を下げただろう。しかし一部からミシャ監督と杉浦大輔コーチ兼通訳への批判がSNSで飛んだ。その中には杉浦コーチの「通訳者としての適性」を問題視する内容もあった。
ミシャ監督が言ってないことを勝手に付け加えたり、ねじ曲げて監督の言葉として浦和サポを揶揄・挑発したりしたのではないか。そういう意見もあった。ドイツ語を理解する人が、ミシャ監督の言葉と杉浦コーチの通訳を比べて、単語通り訳されてないという問題提起が拡散されてもいた。
これらそのものは一理はあり、否定される話ではない。だが僕は「通訳者の役割」に対する批判には疑問があった。サッカーの通訳者は、言葉をそのまま訳すのが仕事ではなく、発話者の意思を伝えるのが仕事だというのが僕の漠然とした思いである。ならばミシャ監督の意思が分からない状態では、仮に単語通り訳されていなくても、それだけで杉浦コーチに問題があると批判するのは難しいのではないか。
もう一点は「通訳者の役割が何か」を、はっきり定義された状態での批判だと思えなかったからだ。一般人と比べてサッカーファンにとって通訳者は身近だ。だから役割をイメージしやすい。
しかしそれは、イメージを自由自在に伸縮も可能だということだ。あるときは「通訳者は意思を伝えるのが仕事」として、正確に単語を訳していてもうまく伝わってないように見えたら批判をし、あるときは「通訳者は正確に訳すのが仕事」として訳が正しくなければ批判をする。どちらも間違いではない。問題は、状況に応じて都合よくどちらかを選択して批判の材料とできることだ。
このようなもやもやを抱えていた時期に、出会ったのが本書である。5人の英語通訳者の日本人にライフストーリー・インタビューした内容と、通訳の学術的観点を組み合わせて通訳の本質にせまった一冊だ。
取り上げられた5人は、主に外交の現場で通訳をしており、スポーツとは関わりがない。しかも会議などの場にのみ同席し、サッカー選手や監督の通訳者のように生活に密着もしない。それでも、通訳の本質を知る参考になると僕が考えたのは、彼らが日本の同時通訳のパイオニアであり、誰もロールモデルがいない中で己の通訳者像を作り上げ、著者をはじめ後世の通訳者の手本となったからだ。
成功は発話者の手に、失敗は通訳者の手に
本書を読むと、通訳が役割を簡単に定義できるほどの正解がないものだと、あらためてよくわかる。5人の見解もぴたりとは一致しない(以下、登場する政治家のポストは、いずれも当時のもの)。
アポロ月着陸の衛星中継をNHKで通訳した西山千さんは、日米貿易経済閣僚会議で河野一郎農林大臣の通訳を担当した。ちなみに彼の孫が「湘南圧勝」でおなじみの河野太郎デジタル大臣である。
「啖呵を切る」という言葉がある。「胸のすくような、鋭く歯切れのよい口調で話す。 鋭い勢いでまくしたてる」という意味だ。あるとき、河野農林大臣はアメリカ農務長官に文字通り「啖呵を切って」すごんだ。怒りを伝えようとしたのだ。ところが西山さんは、河野大臣の言葉のまま訳してしまい、大臣の啖呵は肩透かしに終わってしまった。
西山さんは後に正確な通訳をするには、発言者を良く知り、発言者との間にラポール(rapport)が不可欠だと振り返っている。「心の通い合い」である。
発話者を理解した上での通訳が、誤訳問題に発展したケースもある。「ミスター同時通訳」と称された村松増美さんは、アメリカのロナルド・レーガン大統領の首脳会談のため渡米した、中曾根康弘首相の通訳についていた。
食事会に招かれた中曾根首相は「日本列島を、ソ連の爆撃機の侵入を防ぐ巨大な防衛のとりでを備えた不沈空母とするべきだ」と述べた。これが波紋を呼び、後に批判が通訳者の村松さんに集中した。もともとは中曾根首相の発言内容自体が論争になるはずが、「大きな航空母艦」という言葉を村松さんが「不沈空母」という言葉に変えて通訳したことが問題視されたのだ。
村松さん自身は「ああ訳したのは当然」と本書のインタビューでも言い切った。根拠は、中曾根首相の毅然としたかっこつけた言い方と語調、そして英語の語法である。彼は中曾根康弘という人間を知ってるがゆえに、通訳する言葉を選んだ。
興味深いのが後日談である。この「不沈空母」発言はアメリカの日本に対する不信感を大きく払拭し、中曾根首相はアメリカから大きな信頼を得ることになる。しかし彼は誰が通訳にあたっても結果は変わらなかったと回顧していた。通訳というのは問題になれば責任を負うが、成功すれば発言者の功績となる生き物だということを浮き彫りにする結末である。
西山さんと村松さんの例は、通訳は発話者の意思を言葉だけではなく、さまざまなシグナルからくみ取って訳する仕事だと教えてくれる。そしてその失敗を発話者に代わって被るのも通訳なのだ。
すべては三木武夫のため
われわれがイメージする通訳の役割とは、大きく逸脱した立ち回りをしながらも「同時通訳の神様」とうたわれた通訳がいる。三木武夫首相の通訳をつとめた國弘正雄さんだ。
渡米した際、三木首相はワシントンの外国人記者クラブの会見の最後にこんな質問を受けた。「ワシントンは残念なことにプロ野球のチームがない。ひとつ、東京(読売)ジャイアンツを招致するように骨を折ってもらえないでしょうか」。こういうふざけた質問への返しを見て、政治家の力量をはかるのがアメリカ流だ。三木首相は試されていた。
三木本人は日本語で「私は野球は好きでテレビは見ないが、実況中継だけは欠かさず聞いている。なんとか話を進めてみましょう」と苦笑交じりに答えている。ところが通訳者の國弘さんは「野球はいまでは米国より日本の国技といったほうがよいほど、わが国では人気のあるスポーツ。せっかくですが、ご提案は承諾しかねます」と改変して切り返した。会見は大喝采。実は國弘さんは、最後の質問のときだけは「勝手に作って訳すこと」を事前に三木首相から承諾を得ていたのである。
この会見のおかげだけではないだろうが、三木首相の渡米はアメリカで大きく扱われて成功に終わった。会見での彼の返しが國弘さんの創作だとわれわれは知っている。でも面白いことに、そのときのアメリカ人にとっては「三木首相が言った鮮やかな切り返し」なのだ。國弘さんは通訳者から逸脱した役割を担いながらも、通訳者たる「透明な存在」であったわけである。
彼の「神様」のような通訳の技は、日本人もアメリカ人も高く評価した、超一流の通訳者だった。しかしインタビューで「あんまり通訳、好きじゃなかった」と否定的なコメントを唯一残した「神様」でもある。
そんな彼は「三木さんのときは、がんばったのは事実」と語っている。そのがんばりのひとつが先に紹介した会見での通訳なのだろう。では何が彼をそうさせたのか。
僕は何とかして三木さんを、生意気な言い方でゴメンナサイね、彼を男にしたいと思ったわけ。総理にしたいと思ったわけよ。何とかして総理にしたいと。
自民党幹事長時代の三木から、国際情勢のレクチャーを依頼された際の問答で、國弘さんが彼に惚れ込んだのが始まりだった。憲法を守り、戦争をしない日本を守るために自民党に居続けている三木に、自身の戦争経験から非戦と護憲の思いが強い國弘さんはよりシンパシーを感じた。三木が外務大臣になったときは、通訳者のみならず秘書官となった活躍した。そして首相時代には、とっさの切り返しを見せて三木のアメリカでの評価を高めた。すべては三木武夫のためである。
國弘さんのスタンスは、ある面では通訳者の役割を超えてしまっている。むしろ意図的に逸脱してさえいる。それは本人も認めている。だからといって彼を「通訳者失格」とする者はいない。
仮に三木をサッカーの監督に置き換えたとき、國弘さんのような立ち回りをする通訳者は「通訳者失格」なのだろうか。外交もサッカーも最後は結果だ。通訳者は「通訳者の役割」と「結果」の両方の観点で見られ、時にはその境界があいまいになった状態で良くも悪くも評価される。
そこに情熱はあるか
5人の中で唯一の女性である相馬雪香さんは「憲政の神様」尾崎行雄の子であり、自身の娘・不二子も通訳者となった。
彼女は通訳者に必要なものをきっぱりこう言っている。
どうしてもその考えを片方にわからせたい、その情熱がなきゃ通訳はダメね。
後に彼女は国際会議で通訳をしていた娘・不二子をその場で叱りつけた。それも通訳に必要な「情熱」が関係している。
「相手の痛みを感じない通訳なんか、やめろ」と言ったの。相手の気持ちが伝わらなければ、喜びにしろ痛みにしろ、役に立たない。私は、通訳の基本はそれだと思っています。
通訳者の役割を「情熱をもって発話者の気持ちを伝えること」とするのは少し抽象的すぎるだろうか。だが僕が今後、サッカーの通訳者について考える際は、この原点に必ず思考は立ち返るはずだ。
通訳は言葉を、単語を、正しい意味で伝えるのが本質ではない。言葉だけでなくすべてのシグナルから発せられる気持ちを伝えるのが本質だ。そのシグナルの中で最も正確で情報が整理されているのが言葉である。
だからこそ紹介した通訳者のパイオニアたちも「気持ちを伝えよう」とするあまり、うまく伝えられなかったり、シグナル通り伝えた結果「誤訳」と言われたり、通訳者から逸脱して発話者となったりした。そこに正解と不正解があったかは判断できない。やり方が不正解でも結果は正解かもしれないし、やり方は正解でも結果は不正解かもしれない。だからではないが、通訳者たちの伝える情熱を感じたときは精いっぱいの拍手を送りたい気持ちである。
【本書のリンク】
https://www.msz.co.jp/book/detail/08879/
【次に読むならこの一冊】米原万里・著『不実な美女か貞淑な醜女か』
ロシア語通訳者による名エッセイ。『通訳者と戦後日米外交』と比べると言葉へのこだわりが細かく書かれている。余談だが、来年刊行予定の彼女の父である米原昶(いたる)の評伝の副題が『不実な政治か貞淑なメディアか』だ。小粋すぎる。
https://www.shinchosha.co.jp/book/146521/
【プロフィール】つじー
1993年生まれ。北海道札幌市出身。書評家であり、北海道コンサドーレ札幌とトルコのアダナ・デミルスポルを応援するサポーター。神戸大学法学部法律学科卒業。自身のnoteに毎週に一本、書評のほかコンサドーレを中心としたサッカー記事を執筆している。今月よりポッドキャスト『アラサー男女のいったんそんな感じで』を配信開始。
◎note:https://note.com/nega9clecle
◎X(Twitter):https://twitter.com/nega9_clecle
書評家つじーの「読書コーディネート」
こちらはWM会員の皆様限定の企画です。僕が「読書コーディネーター」として、「いま読みたい本のイメージ」をお聞きしてオーダーメイドでおすすめ本をご提案します!
過去にいただいたイメージは、ざっくりしたものもあれば具体的なものありました。どのような要望でも依頼いただいた方にぴったりの本を必ず紹介します。
興味のある読者の皆様はまず有料部分の「【編集部より】」を読んでいただき、記されたメールアドレスに読書カルテ送ってください。それを元に次回以降、僕がおすすめの2冊を選んだ理由と共にご提案します。
是非ご利用ください。よろしくお願いいたします。
(残り 233文字/全文: 5510文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。
会員の方は、ログインしてください。









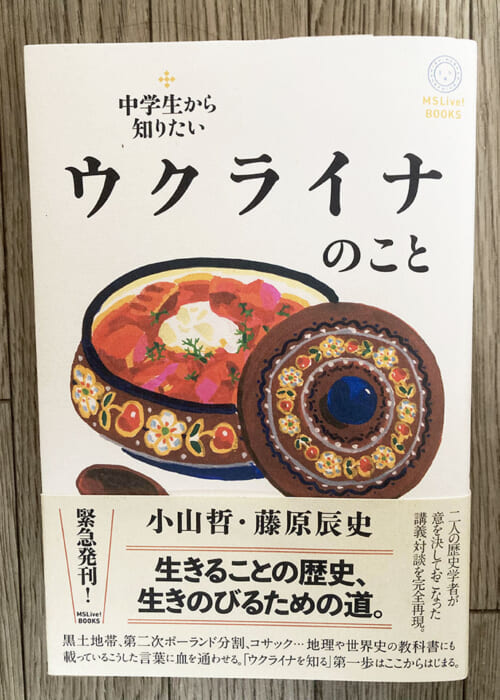




外部サービスアカウントでログイン
Twitterログイン機能終了のお知らせ
Facebookログイン機能終了のお知らせ