『前だけを見る力』松本光平は「ポジティブ」なのか? 筒井香(スポーツ心理学者・BorderLeSS代表)<1/3>
今日(3月21日)は国立競技場で、ワールドカップ2次予選の北朝鮮戦が行われるが、7月にパリで開催される五輪に向けた予選も今がたけなわ。今週は、そんな夢の舞台を目指すアスリートの「伴走者」にご登場いただく。スポーツ心理学者でBorderLeSS代表の筒井香さんである。
筒井さんは1986年生まれで大阪出身。大阪教育大学と奈良女子大学大学院で人間行動科学を学び、2015年に博士号を取得している。現在はスポーツメンタルトレーニング指導士(日本スポーツ心理学会認定)として、さまざまな競技のメンタルトレーニングを手掛けながら、株式会社BorderLeSS代表取締役兼CEOとしてアスリートのセカンドキャリアもサポートしている。
筒井さんとの接点が生まれたのは、私が構成で関わった『前だけを見る力』がきっかけだった。失明の危機という、フットボーラーとして致命的なアクシデントを負った松本光平が、なぜクラブワールドカップ再挑戦を諦めなかったのか。当初、私はその理由を「彼が常にポジティブ・シンキングだったから」と考えていた。
ところが、研究者として彼に対峙した筒井さんは、別の理由を導き出している。ここで多くを語ることは控えるが、スポーツ心理学者としての正鵠を射た彼女の分析は、結果として『前だけを見る力』に大きな説得力を与えることとなった。そうした経緯もあり、いずれきちんと彼女に話を聞きたいと思っていたのだが、それから3年を経てようやく実現することとなった。
メンタルトレーニングの重要性については、五輪やパラリンピックの個人競技では重視される傾向があるが、日本のサッカー界で定着しているとは言い難い。ゲーム分析の専門家はいても、メンタルトレーナーを重用しているJクラブは、まだまだ少数派。それはメンタル面のトレーニングを軽視しているというよりも、むしろ「スポーツ心理学とはなにか」についての理解が、あまり広がっていないことが原因のように思える。
ちなみにメンタルトレーニングは、決してアスリートだけのものではない。筒井さんは今年1月、『シン・ポジティブ思考 しなやかなメンタルのトリセツづくり』という書籍を発表している。ご本人いわく「あらゆる仕事のパフォーマンスを上げる」ヒントが詰まっているとのこと。本稿を読んで、スポーツ心理学に関心を持った方は、ぜひ手にとっていただきたい。(取材日:2024年1月30日、オンラインにて収録)
■スポーツ心理学が「防災意識を高める」ためにできること
──今日はよろしくお願いします。BorderLeSSという会社を経営しながら、スポーツ心理学の研究を続けている筒井さんですが、最近のトピックスとして1月17日の「能登半島地震復興支援チャリティーイベント」が目を引きました(参照)。災害発生が1月1日でしたから、非常にスピーディだったわけですが、どんな経緯で始まったのでしょうか?
筒井 能登半島での地震が発生した時って、私も親戚と一緒に過ごしていたタイミングだったんですよ。日本人が最もリラックスしているタイミングでの災害。「これは大変なことが起こったな」と思いながら、自分の会社で何ができるだろうと考えたんです。まず頭に浮かんだのが「防災意識を高める」。それを私の専門分野である、スポーツ心理学とかけ合わせた時、どんなことが可能なんだろうということを考えました。
──防災というと、防災備品をリュックに詰め込んだり、水を確保したりというものがまず思い浮かびます。けれども筒井さんの専門分野でいうと、むしろ心理面での準備、ということになるのでしょうか?
筒井 実際に災害が発生した時、危険な場所から逃げるだけの体力が必要になります。そのための身体づくりだと、フィジカルの専門家と一緒にやっていくのがいいと思うんですが、心理学的なところでいえば「被災した現実をどう受け止めるか」ということになると思います。とはいえ、決して「ポジティブになりましょう」ということではないんです。
自分たちが酷い目に遭ったとか、自宅や家族を失って辛いとか、そういう苦しい感情を言語化して誰かと共有する。そうすることで、その人の気持ちが多少なりとも軽減されることもあります。そういった、心理的な受け止め方というものは、実は有事の時に有効なんですね。そういったことを伝えられたらと考えました。
──なるほど。これもまた、メンタルトレーニングのひとつなんでしょうか?
筒井 そうですね。フィジカルのトレーニングと違って、メンタルのトレーニングというものは、目に見えないものです。見えないものって、どうしても後回しにされることが多いですよね。けれども、目に見えないものの大事なものがあって、たとえば愛情とか絆とか信頼関係とか。そういった「目に見えないからこそ、心も大切にしていこう」ということは、日頃からセッションの中で言い続けていることでもあります。
──このチャリティイベントでは、具体的にどんなトレーニングを施したのでしょうか。
筒井 私がお伝えしたのは、まず、先ほど言った「感情を言語化して誰かと共有する」という話。それから「主観的な感情を大切にする」という話。これは何かというと、要するに「あの人と比べたら私はまだマシだから」と思ってしまって、辛い感情を押し殺してしまってはいけないということ。実はこれも、けっこう重要だと思っています。
──今回の地震だと「珠洲市の被害に比べたら、ウチの地域はまだマシ」という感じですかね?
筒井 まさにそれです。「家が残ったからいいじゃない」とか「誰も亡くなっていないからマシ」とか。でも、本人が抱える辛さや悲しみというものは、実際には極めて主観的なものであって、何かと比較してもあまり意味がないものだと思います。これは私がアスリートと接する時にも、必ず留意していることでもあるんです。「次の試合で勝てばいいじゃない」と言っても、負けた本人には何ら励ましにはなっていないことは多くあります。
(残り 2246文字/全文: 4694文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。
会員の方は、ログインしてください。


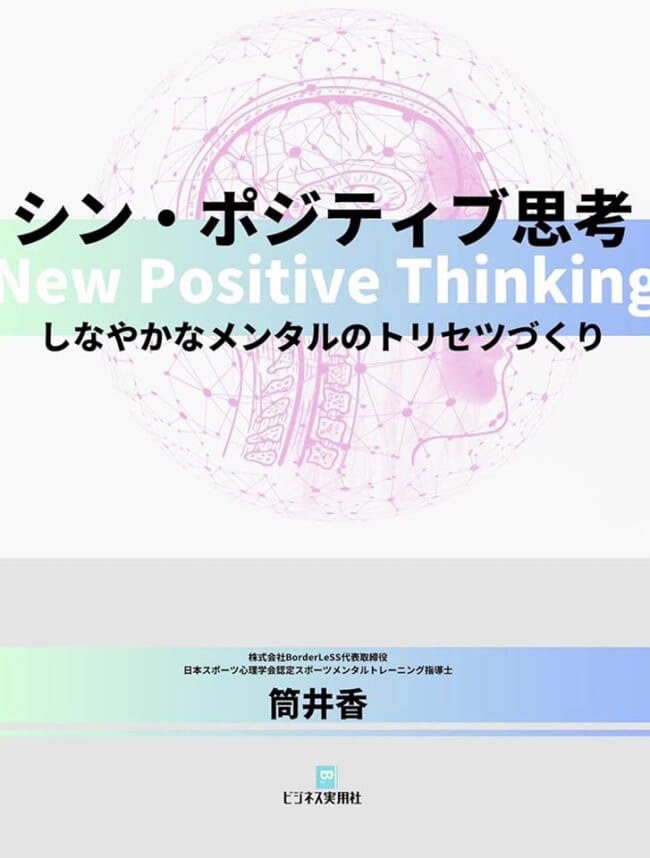










外部サービスアカウントでログイン
Twitterログイン機能終了のお知らせ
Facebookログイン機能終了のお知らせ