【きちゼミ】認知トレーニングとは小難しいことではない。子供の遊びから取り入れながら楽しく取り組むのがスタートだ
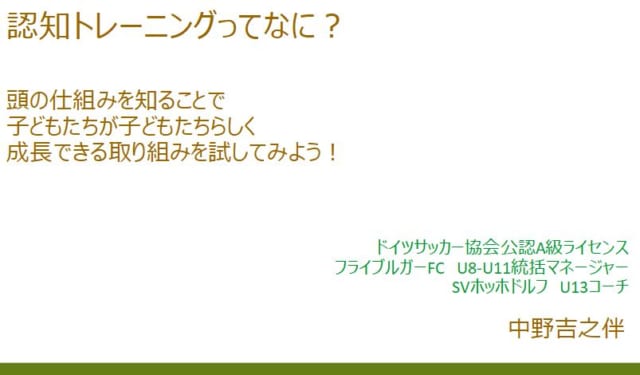
認知トレーニングについて取り扱った前回のWEB講習会に参加された方からの反応をご紹介。また講習会での内容を抜粋でまとめてみたのでそちらもぜひご覧になってください。
▼ 参加者からの反応
「知りたかったテーマであり、分かりやすくお話をされていて、とても貴重な時間でした。」(4種サッカー指導者 曽根裕介様)
「トレーニングには「楽しさ」と「刺激」があると子供達は夢中になる。私達指導者は飽きさせない工夫と魅力のある引出しを準備して臨みたいと改めて思う」(4種サッカートレセンスタッフ 山内尚様)
「お世話になります。本講習会にて、今まで”判断が早い””プレーの切り替えが早い”など、漠然とした認識、言葉で表現していた部分が、理論的に整理できたと感じています。 認知は、幼少からの”遊び”の影響が大きいと感じますが、トレーニングで意識的に向上できること、大変勉強になりました。
遊びという点では、ドイツでのバルシューレに関する取り組み、また認知との関係の話しを伺いたかったです。 また日野市サッカー連盟では、ここ2年ほど前から障がい者サッカーの機会も普及事業で取り組んでおりますが、発育発達障害(大なり小なり人は何かしらもっているものと考えていますが)がある子どもの認知における傾向など、ご存じのことがありましたら、機会があればお聞かせ下さい。
振り返り交流会は都合により参加できませんが、また別の講習会で参加させて頂きます」(4種サッカー指導者 治井 正富)
「認知に関して、どうトレーニングの中で取り組んでいくか、少しずつ整理されてきた感があります。最後の方で他の方が質問されていたのですが、認知をサッカーとどうつなげていくか、というところがとても参考になりました。
ひとつは技術面のトレーニングにくっつける、もうひとつは無理につなげなくてもよい、というところで、肩肘張らずに取り組んで行けそうな気がします。
少人数グループでの交流は人数、時間的に非常によかったです。ただ、日本人的かもしれませんが、ざっくりと話をするよりも、まず話す内容、テーマをある程度決めていただいていた方が進行がスムーズかもしれません。
最後に、延長戦で色々な話をされていて、ああいった中で色々な話が聞けるのは大変ありがたいです。オフザピッチの教育のこと、指導者の空気感のこと、色々と考えさせられます。 今回も大変勉強になりました。ありがとうございました」(4種サッカー指導者:大森健太様)
「早速日曜日に教えていただいたものを取り入れました!とても楽しそうにしており、その後の集中力にもつながったかと思います。自チームで認知トレは取り入れているのは取り入れているのですがやはり量が少なかったことが今回の気づきでした。
遊びからサッカーに係る認知トレーニングを知れたので今後は増やしていこうと思います」(匿名)
「今回は、幼児教育という分野から参加させていただきましたが、認知トレーニングが発達心理とも密接な関わりを持つこともあり、大変興味深い学びをいただきました。 特に、最後のルーカス・シンキビッツ氏の「育成の間にもっともっと自分でミスをさせるんだ。」という言葉が印象に残っています。
日本では、ミスをすると、監督やコーチから怒鳴られたり仲間から責められたりする場面をよく見ます。ジュニアユースやユース世代になると反骨精神で頑張る選手もいるかもしれませんが、ジュニア世代だと、「ミスをしたら怒られる、責められる」といった認識が植えつけられ、意欲や自己肯定感の低下につながることが懸念されます。
サッカーに限らず、「ミスをすること」をもっと肯定的に捉え、成長のチャンスだとすることが大切なのだと改めて感じました。 また、機会があれば、講習会に参加させて下さい。 今後のご活躍も楽しみにしております」(保育園関係者 匿名)
「認知トレーニングについて、日本サッカー協会からの印刷物等の特集で見た記憶がありませんが、とても大事なことだと思います。協会は何をしているんだ!と思いました。 認知トレーニングを行った場合と行わなかった場合の違い、といった実績が計測されていれば、それも知りたいです(特に子どもについて)」(4種サッカー指導者 匿名)
(残り 1988文字/全文: 3769文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。
会員の方は、ログインしてください。





外部サービスアカウントでログイン
Twitterログイン機能終了のお知らせ
Facebookログイン機能終了のお知らせ