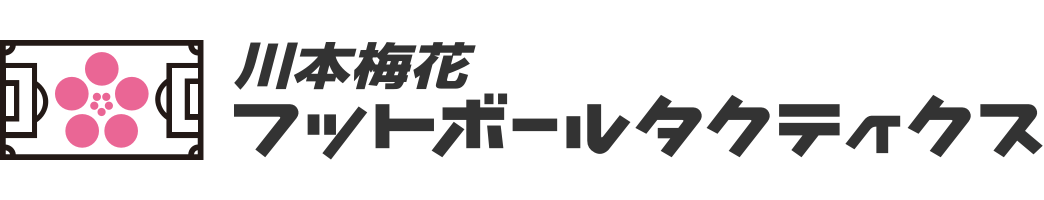【試合分析】超えられそうで超えられない壁 J2第35節 #鹿児島ユナイテッドFC 1●0 #水戸ホーリーホック #mitohollyhock
超えられそうで超えられない壁
サッカーだけを見れば、ビルドアップからゲームを作ろうとする水戸と、ビルアップをまったく放棄して戦った鹿児島の試合は、チーム力では測れない「何か」がそこにはある、と思わさせられた。
目次
■両チームのシステムを組み合わせる
■失点の場面を見てみる
11月16日土曜日 15:03 キックオフ 白波スタジアム
2019明治安田生命J2リーグ第41節
鹿児島ユナイテッドFC 1⚫︎0 水戸ホーリーホック
https://www.jleague.jp/match/j2/2019/111611/live/
■両チームのシステムを組み合わせる
水戸ホーリーホックのシステムは、「4-4-2」の中盤をボックス型にする。試合中の状況で、「4-4-1-1」のフォワード(FW)が縦関係になることがある。鹿児島ユナイテッドFCは「4-2-3-1」のシステムを採用している。両チームのシステムを組み合わせてみると、基本的にマッチアップ状態になっている。それ以外のポジションは、2対1で水戸の数的優位の場所がある。それは次の組み合わせだ。
前寛之と白井永地 v.s. 枝本雄一郎
細川淳矢と宮大樹 v.s. 韓勇太
2対1で水戸にとっては数的優位になるのだが、実は、難しいシチュエーションであったりする。鹿児島の選手の動きによって、水戸の2人のうちのどちらがマークに行くのかに迷いが出てくる場面が訪れる。その時に、きちんとマークできるのかどうかが興味深いところだ。

■失点の場面を見てみる
水戸のセットプレーの守備は、基本的にマンツーマンとゾーンの併用で守っている。「誰が誰をマークする」というマンツーマンは、きちんと決められている。ヘディングが強い相手選手にはぴったりとマンマークする。さらに、ニアサイドに1人選手を置いて、鹿児島のキッカーが蹴る低いボールやゴールキーパー(GK)の手前にくるボールを防ぐ役割を担う。
攻撃する鹿児島は、キッカーがボールを蹴る前にペナルティエリア内に数人の選手がひと固まりになってから、それぞれ散らばっていくやり方をする。初めから相手にマークをさせないように狭い場所で競り合わせる。キッカーがボールを蹴ると、いっせいにゴールのニアサイドとファーサイドと中央に選手が入っていく。

細川は水本勝成に、宮はニウドをマークする。得点した韓には清水(あるいは白井)がついていたと思われる。FWの韓がゴール中央に入っていくと、白井と清水慎太郎が行く手を防ごうと体を寄せる。この場面は、一人のサッカーライター(試合分析者)として見れば、迫力があって見応えのあるやり取りが行われている。体を張ってブロックしている白井を、韓が体をぶつけてはねとばす。清水も韓の前に立って蹴られたボールをはねのけようとした。しかし、韓は清水よりも高く飛んでヘディングをしてゴールを決める。結果的に失点をしたのだから、マークしているのに得点を与えたとして、マーカーのミスを責めることはできる。この場合は、得点者の韓を称えるしかないかもしれない。
もしミスがあったとすれば、コーナーキックを相手に与えたシーンを防ぐ大切さに欠けていたとは言える。本当に細かいことの改善は必要だ。コーナーキックを相手に与えることさえも許さないという戦う厳しい姿勢が。特に、お互いのチームが、こういう状況においてであるから。だから、失点に関しては、マークするべき選手のマークを外したとか、相手選手をまったくのフリーにしてしまったものではない。そうした中での韓のあの得点は、驚愕すべき出来事だったと思われる。
西村卓朗ゼネラルマネージャーとの関係から水戸ホーリーホックの試合をここ数年見てきた水戸の新参者の私は、この試合を見終わって、なぜか、涙が出てきた。超えられそうで超えられないものがあるのか、という思いが沸き起こってきてしまったのだ。「勝って欲しかった」という自分の感情に少し恥ずかしくなった。サッカーを見ていて、こういう感情を持ったのはいつ以来なのだろうか、と振り返った。
サッカーだけを見れば、ビルドアップからゲームを作ろうとする水戸と、ビルアップをまったく放棄して戦った鹿児島の試合は、チーム力では測れない「何か」がそこにはある、と思わさせられた。その「何か」とは、決められる時に決められる絶対的な存在者の不在に対する「何か」なのか。それとも、もっとチーム力を高めて得られる「何か」なのか。最終節の試合を見るまで、その答えは出てはこないのだろう。
川本梅花