スイーパー大好き少年が審判の面白さに目覚めるまで 家本政明(元プロフェッショナルレフェリー)<2/3>
■レフェリーになれば「俯瞰して見る楽しみが2倍以上」!
──家本さんがレフェリーという職業を意識するようになったのは、1986年のワールドカップ・メキシコ大会で主審を務めた、高田静夫さんの勇姿をTVで見た時だったそうですね。それが13歳の時だったと思いますが、ご自身で笛を吹くようになったきっかけは何だったのでしょうか?
家本 高校生の時に、監督から「ちょっとやってみないか?」と言われたのがきっかけでした。ちょうど内臓の病気で試合に出られていなかったので、2~3試合やってみたんですが、プレーヤーとは違った面白さを感じました。
──私も高校時代は下手くそな補欠部員だったので、当時でいうところの「ラインズマン」をやらされたんですが、まったく面白くなかった(笑)。家本さんはどのあたりに、レフェリーの面白さを感じたんでしょうか?
家本 もともと僕は、試合を俯瞰して見るのが好きでした。それを活かせるのが、当時のサッカーのポジションでいえば「スイーパー」。僕らが中学くらいの時まで、DFの後ろにスイーパーっていたじゃないですか。その後、フラットなディフェンスラインが主流になりましたけど。
──そうですよね。特定のマーカーがいなくて、こぼれたボールをケアするのがスイーパーの主な役割でしたけれど、やっぱりゲームを俯瞰できるから好んでプレーしたのでしょうか?
家本 そうですね。味方と相手の考えていることとか、試合全体の流れとか、そういったことがスイーパーのポジションからは強く感じることができました。僕はGK以外のすべてのポジションを経験しましたが、やっぱりスイーパーが一番やっていて面白くて楽しかった。これがレフェリーになると、俯瞰して見る楽しみが2倍以上になるわけですよ。
──非常に興味深い感覚ですね(笑)。その後、同志社大学に進むわけですが、吐血したことが原因でドクターストップがかかってしまい、競技者としてのキャリアに終止符が打たれることとなります。これもまた、家本さんがレフェリーを職業にする大きな契機となったわけですが、それ以外の選択肢はなかったのでしょうか? たとえば指導者とか。
(残り 2776文字/全文: 3731文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。
会員の方は、ログインしてください。





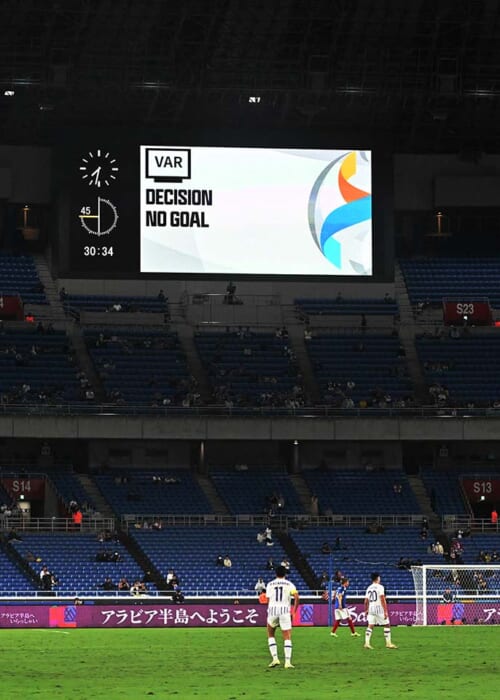







外部サービスアカウントでログイン
Twitterログイン機能終了のお知らせ
Facebookログイン機能終了のお知らせ