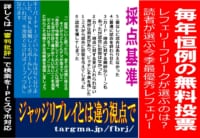無料:日本サッカー協会やJリーグ担当審判員がエルファス・イスマイルから学んだマネジメントの『ACT』【レフェリーブリーフィング4.3④】
4月3日、日本サッカー協会(JFA)審判委員会が今年第二回目となる『レフェリーブリーフィング』を開催した。
扇谷健司JFA審判委員会委員長の簡単な挨拶の後で、佐藤隆治Jリーグ統括マネジャーが交換プログラムで来日したエルファス・イスマイルのレフェリングについてメディアに分かりやすく“審判批評”した。
「このように色々な学びがありました。イスマイルのレフェリングですが、彼は身長も大きいですし、見た目も怖い(強い)ですよね。彼から一番学んだ“(レフェリーって)そうだよな”と思ったことはマネジメント。選手とのマネジメントで非常に学びが多かったので、(担当した試合の町田ゼルビア×鹿島アントラーズ戦を)映像にまとめました」
4分、鈴木優磨のチャレンジが遅れて足に入ってしまったため、ファウルをとり、鈴木はもちろん、ファウルを受けた仙頭ともコミュニケーションをとる。
「通常ファウルがあって注意をする時、このシーン負傷者もいます。日本のレフェリーは負傷者の対応をするのですが、彼は二つの選択をします。
ファウルをした選手にマネジメント、注意をしたい。
でも負傷者のケアが大事。
イスマイルは、鈴木選手に対し『ここにいなさい』とジェスチャーで示します。
そして、負傷者のケアに行って、確認した後で、鈴木選手に対面をして話をする。
早い時間帯ですけど、ここでface to feceでコミュニケーションをとります。海外はface to feceを重要視します。彼は目を見て話をする事を心がけているということで、この場面でもそうするために、鈴木選手に『ここにいなさい』と先に示しています。
ただ、「ですので、若手のレフェリーにもこのようなマネジメントをしなさい」は難しくて、やはり日本人は外国籍選手、外国に対してリスペクトをしすぎるケースもあると思うので、(日本のレフェリーがJリーグで)このマネジメントで巧くいくかは別問題。
彼がこのマネジメントを選択したのは、この試合の前に鹿島の試合を見てから試合に臨んでいます。(中心選手やチームやゲームに与える影響等を考えて)ここは試合を止めて話をする必要があると判断した。
彼のマネジメントは、バラエティー豊かというか、引き出しが多かったです。」
15分の遠目からジェスチャーで表現力を発揮。
「ここは決して近付いて距離を縮めないのですが、正対をしてレフェリーのメッセージを発信しています。」
19分、こぼれたボールを自分で保持しようとしたバスケス・バイロンが、故意ではないものの足にもチャレンジする格好になったためラフプレーで警告。
「鹿島の選手がこういった(serious foul playが起きたような)リアクションするのもわかるような(ラフプレーのシーン)。選手たちは“よくないファウルじゃないか”とカードを要求しているのが見えます。
この時のレフェリーの立ち振る舞い、もう慌てずにどっしり構えて『自分が見ている』『自分にまかせてほしい』とまず鹿島の選手に対応しながら争点に向かって、治療の対応をする。いつも治療が先ではなくて、4分のケースと違いますよね。この時は、選手がレフェリーの元にアピールに集まっていますから、『自分が見ている』『自分にまかせてほしい』と落ち着かせた上で、次に進んでいる。
バリエーション豊かなマネジメントはひとつひとつ見ていても興味深い。
彼がオンラインの研修会で言っていたのは、『ACT』つまり『なりきる』『立振る舞い』です。
日本人は真面目ですごく礼儀正しいのですが、それが逆に外では弱々しく見えてしまって、レフェリーとしての威厳やPresenceを下げている部分もある。そこで『ACT』『自分を演ずる』ということも大事だと思っています。」
24分にはロングスローのポジション争いに注意を与え、大きな判定が起こるのを防ぐ。
「最後はロングスローからのシチュエーションですが、セットプレーのシーンでは、ゴール前の引っ張りあい、押したり、ブロックしたり等、色々な事象が起きています。
映像だけでは何を話しているか分からないかもしれませんが、このジェスチャー、立ち振る舞いを見ると、選手に何を伝えたいかがよくわかる。
話過ぎるのもよくないですし、何でもかんでも時間を掛けすぎるのもよくない(彼はその辺の切り方も巧い)。
このようなマネジメントをそのまま真似するとかではなくて、吸収して、自分のやり方で表現できるようにしたい。そういった意味でイスマイルから非常に学びがありました。」