「我々審判員は選手の安全を守る。その為にも的確な判定をするのと同時に、皆さんにも配慮のある行動をお願いしたい。危険な行為での怪我、長期離脱は避けたい」【2021第三回レフェリーブリーフィング前編】
7月9日、Zoomにて『2021年第3回レフェリーブリーフィング』が開催された。
今回のトピックスは3つ。「ハンドについて」「J2の危険な行為について」「VARについて」扇谷健司JFA(日本サッカー協会)審判委員会副委員長が説明を行ったので、詳細をレポートしたい。
*大まかな無料記事はこちらから
J2第19節 群馬×町田 71分のシーン
扇谷副委員長
「近くにいる味方競技者が急にヘディングしたボールが、事象の選手の方に向かってきて、右手に当たったというシーンです。当たった選手の右手というのは不自然に大きくはされていません。
今までですと、こういった場面で、少し腕が広がってたり、肩より高く腕が上がっていたりすると、ハンドになるケースもみられました。
ですが、今回の改正により、ハンドの反則にはならないことが明確になりました。サッカー競技の中で妥当性を求めるたのだと思います。
皆さんもご存知だとは思いますが、このシーンを何度もスローモーションでリプレイを見れば、ハンドのように見えます。それは非常に危険な見方で、ノーマルスピードで見れば、ハンドではないのはご理解いただけると思います。」
J1第20節 湘南×柏 48分のシーン
「これはバリアに近い考えですね。バリアという言葉は競技規則には記載されていませんので、不自然に大きくされた腕という言葉で説明した方が良いのかもしれません。いずれにしろ、至近距離でも、このように腕を広げるとハンドの反則になります。」
J3 13節 讃岐×熊本 7分
「前回のブリーフィングでも、J3を取り上げることがあまりなかったので、それもあり、J3の事象をご説明します。
競技規則が改正され、たとえば選手同士が接触した時に、そのはずみで腕が上がってしまい、そこにボールが当たった場合はハンドの反則とは見ないという説明をさせて頂きました。
ですが、今回のケースでは、そもそも讃岐の選手の腕が上がっています。さらにいえば、選手は誰とも接触しておりません。自分からボールに向かって、結果的に左腕を高く上げてしまっている。
こういったケースは、今までも当然ハンドだったと思いますし、今後も変わりません。腕を広げて、体も大きくしています。」
*ハンドの反則にならないように配慮する選手たちのプレー映像が流される。
「6月19日の改正以降、ハンドの反則への選手たちの配慮も見えてきています。
前回、ハンドの反則の改正の説明をさせて頂いた時にもですが、腕を後ろに回す守備を私たちからお願いすることはない(審判は選手のプレーに介入しない)とご説明しました。
我々が言えるのは、あくまでも選手の皆さんが、リスクを感じてどのような対応を出来るかということなのですが、このように少しずつ選手の皆さんの配慮が見えてきているというのが現実だと思います。それは選手の皆さんの努力で、なるべくハンドの反則にならないように配慮をされている。
6月19日以降、今までハンドとしていたものがノーハンドになったという事象はほとんどありません。黛(俊行JFA審判委員会)委員長から「多少の混乱は生まれるかも」という懸念がありましたが、今の所、混乱はなかったと思います。」
(残り 1988文字/全文: 3348文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。
会員の方は、ログインしてください。





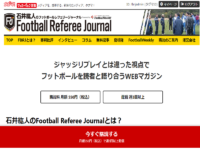




外部サービスアカウントでログイン
Twitterログイン機能終了のお知らせ
Facebookログイン機能終了のお知らせ