すったもんだだった学校選びを振り返る。比較検討したくても資料が10分間の動画しかなかった件
こんにちは!水曜日の無料コラム「ゆきラボ」です。今日は前回のコラムの続きとして、今年小学校を卒業する子どものいる家庭が直面した学校選びをレポートしたいと思います。
前回書いたように、ドイツの小学4年生の子どもは、学校での成績や態度を基準に、どの学校に進学できるかが書かれた推薦状を4年生の冬に受け取ります。もし私たち家族がもう少し小さな市町村に住んでいれば、学校の選択肢がそもそも限られているので、この時点でほぼ自動的に進学先が決まります。
ですが、人口20万人のフライブルクには公立のギムナジウム(大学進学を目指す8年制または9年制の一貫校)だけでも数校、私立や特別カリキュラムを持つ学校も含めると10校近い選択肢があります。
通常ならば11月末か12月にこれらの学校が一堂に会する合同進学説明会があるのですが、2020年はコロナ禍のため中止に。代わりに分厚いパンフレットが何部も配られ、さらに各学校がオンラインで学校紹介のビデオを公開し、ビデオ通話または電話(!)で個別に学校の進路担当者と面談もできることになりました。

イメージ:https://www.photo-ac.com/
この1校10分程度の学校紹介のビデオですが、実際の学校の良し悪しを別にするなら、字幕や効果音、静止画資料などを差し込んでテンポ良くまとめられた見やすいものから、カメラの前で校長がひたすら学校の方針や特色を話すだけの残念なものまで、クオリティは千差万別。ネット時代に強い教職員がいるかいないかが一目で分かってしまいます。急に今まで作ったことのないものを作って公開しなくてはならなかった教職員の皆さんのご苦労もしのばれますが、これを参考にどの学校に行きたいか決めろと言われてもかなりしんどいものがあります。
何校かのビデオを見ましたが、ビデオだけでは決め手らしい決め手にならず、結局以前から目星をつけていた、
・家から自転車で10分、長男と同じ9年制ギムナジウムA
・通学はトラムで30分、温かく丁寧な校風に定評のある8年制ギムナジウムB
の2択で迷うことになりました。

イメージ:https://www.photo-ac.com/
日本の学校と異なり、ドイツにはいわゆる偏差値のような学校のレベルを図る物差しがありません。親は主に
・自宅から通いやすいかどうか
・語学や副教科の選択で、子どもに合った選択肢が用意されているかどうか
・校風が子どもに合っているかどうか
・校外活動や課外活動の充実度
などを基準に学校を選びます。
公立普通科のギムナジウムの場合、入学試験はありません。学校側は自分の学区に近い子どもと、既にその学校に在学している子の弟妹を優先的に入学させるというルールがあるので、いくら小学校での成績が良くても、自宅から遠い学校に願書を出すと入学できないこともあるという、日本の受験を経験した人間からするとちょっと謎なシステムが存在します。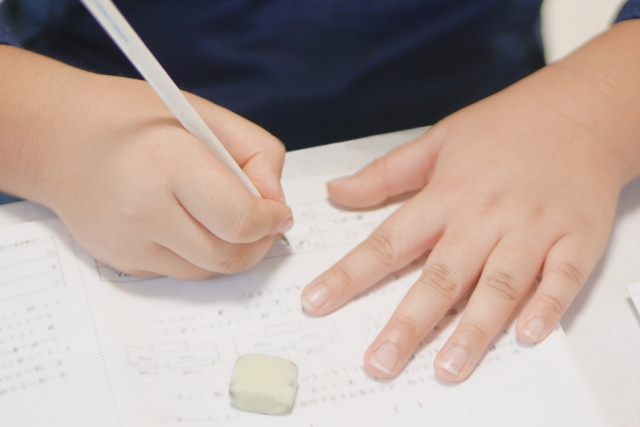
イメージ:https://www.photo-ac.com/
ギムナジウムAを選ぶなら、我が家は学区内ですし、長男も既に在学しているので、次男もほぼ確実に入学できます。9年制を採用しているので、他の公立校よりもカリキュラムに少し余裕があるのも魅力です。ただ、市内で一番生徒数の多い大規模校なので、周囲の環境に気分を左右されやすいところのある次男には、大規模校独特のにぎやかな雰囲気が合うのかどうかは正直疑問でした。
ギムナジウムBの場合は学区外なので、学区内の子どもだけで定員に達した場合、次男はふるい落とされる可能性があります。定員が何人で、それに対して何人の申し込みがあったのかを事前に知るすべはありません。8年制ですが、保護者と連携して子ども一人一人に寄り添った指導をしてくれ、落ち着いた静かな雰囲気の校風がとても評判の良い学校です。
ほぼ確実に入れて、家からも近いけれど、校風が子どもに合っているかどうか疑問な学校と、応募の段階で落とされる可能性があって、家からも少し遠いけれど、もし入れれば親身になって子どもをサポートしてくれる学校。
もしあなたが小学4年生の子どもの親だったら、どちらの学校を選びますか?
次回のコラムに続きます。今週もお読みくださりありがとうございました!





