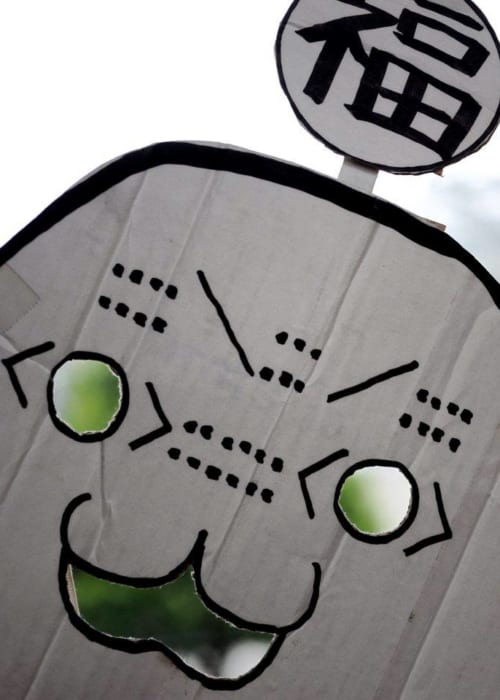【無料公開】書評家つじーの「サッカーファンのための読書案内」第13回 多木浩二『スポーツを考える』
2024年1月からこのマガジンで「サッカーファンのための読書案内」として、サッカーと関係のない本をサッカーに結びつける形で紹介をする連載をさせていただいている。今年も連載を継続させていただけることになった。
2025年の「サッカーファンのための読書案内」は、紹介する本とともに、自分が気になった最近のサッカーニュースや記事を取り上げる。一冊の本を補助線に、サッカー界のトピックを読み解いていく試みだ。
サッカーのことは、サッカーだけを考えていても深く分からない。サッカー本以外の本にもヒントがあるのではないか。引き継ぎ、この思いを持って連載を続けていきたい。どうぞ、よろしくお願いいたします。
アビスパ福岡の新監督就任から考える「サッカーとは何か」
昨年末、アビスパ福岡が金明輝新監督就任を発表し、Jリーグファンの間で大きな話題になった。
彼はサガン鳥栖U-18、またはトップチーム監督時に、選手やスタッフに暴言や暴力行為を繰り返したとしてパワーハラスメント行為が認定され、S級コーチからA級コーチへの降格処分がくだされた。
その後、FC町田ゼルビアのヘッドコーチを務めながら、S級コーチの資格を回復し、今回の監督就任にいたった。
パワハラの前科がある人物が、同様の役職に再びつくことへの疑問や不安視が飛び交う中、今回のクラブの対応に関連して長年大口スポンサーをつとめていた地元企業が、契約を満了する事態にまで発展した。
この話題に関して、僕は福岡の公式サイトに掲載された新監督就任記者会見要約書を読み、これは「サッカーの価値」や「そもそもサッカーとは何か」について、あらためて考えるきっかけになると感じている。
そもそもサッカーとは何か。これを考えるのにうってつけの本が、多木浩二著『スポーツを考える』である。
彼は芸術学を専門としながら、写真、美術、建築、思想、そしてスポーツなど、多彩なジャンルを縦横無尽に論じた評論家だ。取り扱っているテーマは、近代スポーツや近代オリンピックの成り立ち、記号論や身体論、スポーツと消費などである。
この本が刊行されたのは1995年。奇しくもアビスパ福岡の創設と同じく30年前だ。その内容は、今でもまったくさびついていない。テクノロジーがより進化し、スポーツを取り巻く環境も劇的に変化しているにも関わらず、だ。
闘争から暴力を取り除いたスポーツ
金監督自身は「自分自身の過ち」として反省をしているようだし、彼の過去の行いそのものを具体的に取り上げることはしない。その代わり、ここではあらめて「サッカーと暴力」の関係について考えていきたい。
暴力はいけないこと。これは今の社会では自明の話だ。だからこそ、暴力や暴言をともなうパワハラは悪とされている。
その反面、サッカーは「戦争」「闘い」「闘争」といった激しい言葉で形容されるスポーツでもある。
これらが暴力を暗示しているわけではないが、「戦争や闘争に勝つためには、選手やスタッフなどチームに強い『圧』で臨まないとチームを本気にさせれない」というひとつの考えにつながり、その延長線に暴力や暴言が発生することは否定できない。
金監督の就任と同じタイミングで、あるサッカー解説者がDAZNの番組にて「ノーファウルでルール内であれば、相手を壊すことも考える」といった趣旨の発言をしたようだ。
意図して相手を壊すまでいくと、それはラフプレーではなく暴力に匹敵するのではないだろうか。
どうやらわれわれは「サッカーは戦いなのだから、どうしても暴力と近い関係性になりかねない」という意識が刷り込まれているのではないか。
それが行き過ぎると「サッカーだから、日常じゃ許されないラインも多少は許される」という認識につながってしまう。
多木は、サッカーをはじめとした近代スポーツの成り立ちに関して、ノルベルト・エリアスの理論を紹介している。エリアスによれば、近代に誕生したスポーツの特徴は「非暴力の競争」にある。
身体の闘争にもかかわらず、暴力的な要素はいっさい除かれ、身体の振る舞いに対して、ある程度の規則(ルール)が課される。闘争だけど、相手を傷つけてはならない。死にいたらしめるなんてあり得ない。
サッカーの原型とされる、中世以来行われてきたモブフットボールと、現代のサッカーとの大きな違いは、暴力性の排除に尽きる。つまり、サッカーはそもそも「暴力を排除」したうえで成り立っているスポーツなのだ。
この成り立ちと原則を踏まえると、サッカーの世界に何らかの形で暴力が持ち込まれることは、いかにサッカーとミスマッチであるか、理解できるだろう。
サッカーの成り立ちから考えれば、むしろ暴力は「サッカーだからこそ、厳しく排除しなくてはならない」のではないか。
一般論だけでなく、こういった視点からも、サッカーにおけるパワハラがどんな意味を持つのか、考えることができる。
高く見積もられすぎるサッカーの価値
金監督の就任会見で、僕が一番気になったのが、川森敬史会長による次の発言である。
監督自身が過去をしっかりと反省し、努力を重ねてきております。そして、過去の間違いを乗り越える過程もまた、子どもたちにとって大切な学びや刺激になると信じております。チームスポーツであるサッカーを通じて、チーム全体が新たなことに挑戦 し、前進し続ける姿勢を子どもたちに見てもらい、何かを感じてもらうことも大事なことかなと 確信しております。
どうしてもよくわからなかったのが、U-18の選手、つまり子供たちに暴力や暴言を行い、処分された人物の更生が、何をどうしたら子供たちの大切な学びや刺激になるのだろうか、という点だ。
「ああいうことをする大人になっちゃいけません」という反面教師とでもいうのだろうか? もちろん、そんなつもりで言ったわけではあるまい。僕なりに解釈すると「サッカーだからこそ、サッカーで過ちを犯した人が立ち直る姿や結果を示す姿が、ポジティブなものをもたらす」ということになる。
この発言から僕が感じるのは、川森会長が「サッカーの価値を高く見積もりすぎているのでは」ということだ。とはいえ、サッカーに大きな力を信じ切っている人ならまだしも、一般社会の感覚では理屈として腑に落ちない発言ではないだろうか。
サッカーはプレーする人や、それに関わる人たちだけのものではない。ファンを含めた「観る人間」のものでもある。
そんなことは「サポーター側からのきれいごと」と思っているサッカー関係者がいるかもしれない。
だが多木は、そもそもスポーツという概念が発生時から観客を含めた社会(社交)の中で成立してきたと説明している。彼に言わせれば「なぜ、人はスポーツを観るのか?」という問いは、その設問自体が間違っているのだ。
サッカーは社会の中で成立しており、その社会には初めから「プレーヤー」だけでなく「観る人」も含まれているのだ。
だからこそ、サッカーの世界にいる人間は、社会の感覚に敏感である必要があるのではないか。それが「観る人」や、その予備軍である一般人の感覚である。
サッカーの力を信じるのは大切だ。僕も信じたい。でも、今の社会の感覚に合わないことが「サッカーだから大丈夫」なんて認識は、サッカーというスポーツの成り立ちを理解できていないことになってしまう。
多木の論考は「スポーツとは何か」を、あらゆる角度から徹底して考えている。そして彼の著書を読むことは、すなわち「サッカーとは何か」を自らに問いかけることにもなるのだ。
【取り上げた本】多木浩二『スポーツを考える』
https://www.chikumashobo.co.jp/product/9784480056474/
【取り上げたニュース】
新監督就任記者会見要約書(アビスパ福岡公式サイト)
https://www.avispa.co.jp/news/post-74603
【プロフィール】辻井凌(つじー)
サッカーが好きすぎる書評家・文筆家。北海道コンサドーレ札幌とアダナ・デミルスポルを応援している。自身のnoteに本の紹介、歴史とサッカーの関わり、コンサドーレの話題などを書いている。
◎note:https://note.com/nega9clecle
◎X(Twitter):https://twitter.com/nega9_clecle