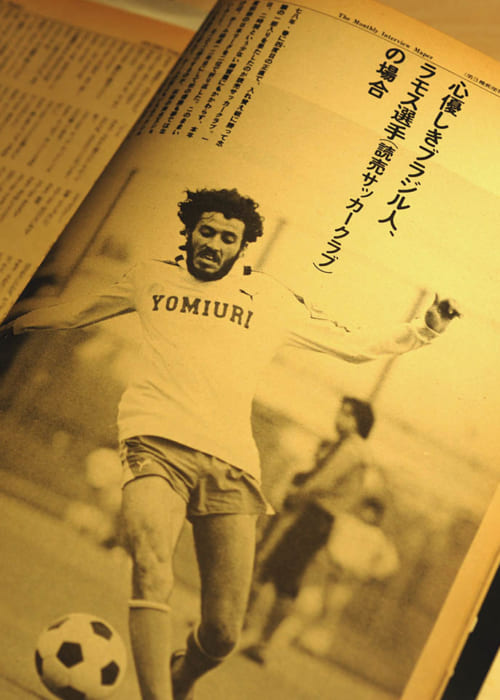【無料公開】『電通とFIFA』の著者が語る 「スポーツ村のドン」 高橋治之の原点<2/2>
■「捏造記事を許すな」をあえて書いた理由とは?
──ところで田崎さんは、最近の『フットボール批評』で「捏造記事を許すな」という記事をお書きになって、かなり反響があったようですね。FCバルセロナのルイス・エンリケ監督のインタビューが「実際には取材していないのではないか」という問題提起でしたが、そういう疑わしい話は、これまでにもないわけではなかったんですよね。
田崎 まあ僕は、サッカー界の人間じゃないんで書けたんですけど。ただ、タイトルについては、編集長の森(哲也)さんが走り過ぎかなと(笑)。さっそく『サッカー批評』の双葉社からカンゼンに質問状が行ったみたいですね。
──田崎さんとしては、これはもう確信をもって書いたわけですよね。
田崎 もちろん、確信はあります。ただ誤解してほしくないんですけど、僕は双葉社やカンゼンがどうこうということには、あまりこだわっていないんですよ。ここで訴えたいのは、スポーツライティングの世界にはびこっている「安易な仕事」や「いい加減な仕事」なんですよね。ライターがどこまでちゃんと取材しているのか怪しかったり、編集者も引用文献をどこまで引用しているのかわからなかったり。そうしたことが「なあなあ」になっている原稿は、けっこう増えているんですよね。
──ライティングや編集の劣化については、私も思うところがあります。単純な話、メディアにお金と時間の余裕がなくなって「取材費は出せないし、原稿料は安いけれど、PVは取りたい」という方向にずっと進んでいるじゃないですか。しかも編集者についても、きちんと後輩を教育している余裕もない。ベテラン編集者もまた、紙から急にネットにシフトして、それまで培ってきたスキルがまったく活かせないことに戸惑っている。
田崎 うーん、何をもってプロの編集者なのか、何を持ってプロの書き手なのかっていうのは本人たちも理解していないように思えるんですよ。具体的に言えば、いわゆるWebメディアの編集者は、本来的な編集の意味がわかっているのか、不安に覚えることがあります。
文字校正するだけじゃないんですよね、当たり前ですけど(笑)。原稿の元になるインタビュー起こしひとつとっても、ものすごく雑で基本的なことがわかっていない。どうも僕らの世代が若いときに経験してきた、先輩からのスキルの継承というものが、きちんとできていないんじゃないかと思うわけですよ。
──それは確かにあるかもしれませんね。スキルの継承というのは、要するに教育だと思うんですけど、自転車操業の状態になると、まずその部分が疎かになりがちです。
田崎 今回は『フットボール批評』で『サッカー批評』の問題点を告発しましたが、『フットボール批評』の編集部も問題がないとはいえない。だから僕はあえて、自分の仕事の仕方というものもできるだけ見せるようにしています。そこで感じたものを、彼らが後輩に伝えてくれるといいんですけどね。
いずれにせよ、仕事の仕方とかスキルの継承とか、そういったものを「ネット社会だから」の一言で片付けてしまうのは、僕は危険だと思います。今回の告発記事も、そうした業界全体に感じる「緩み」みたいなものを糺すことが第一の目的ですね。
──話は尽きないですが最後に、次の取材テーマについて教えてもらえますか?
田崎 今、『KAMINOGE』という雑誌で初代タイガーマスクとしても知られる佐山サトルさんの評伝の連載と、『実話ナックルズ』で「絶滅芸人」という連載をしています。1回目は月亭可朝師匠ですが、まあ皆さん、破滅的な人ばかりで大変ですよ(苦笑)。芸人さんというのは、ある意味「動物」ですから。
──動物なんですか(笑)。
田崎 そうですよ(笑)。アスリートもそうでしょ。だから書き手であるこっちは「僕は貴方のことは好きだし、ちゃんと書きたい。でも負けないよ!」という感じで接するしかない。インタビュー取材というのは基本そういう対決だと思います。
──なるほど(笑)。今後は、サッカーやスポーツにこだわらずに取材していくご予定ですか?
田崎 もともとスポーツライターではないんで(笑)。もちろん、気になるアスリートもいないわけではない。けれど、ものすごく興味があるサッカー選手が今はそんなにいないというのが正直なところです。
──次回作に期待しています。今日はありがとうございました!
<この稿、了>