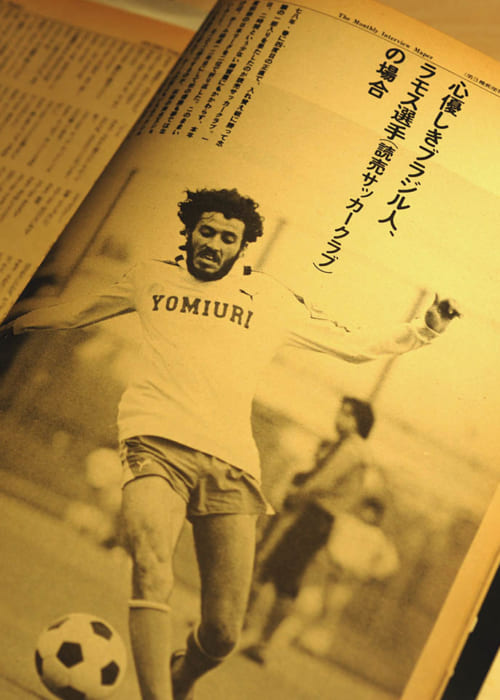【無料公開】『電通とFIFA』の著者が語る 「スポーツ村のドン」 高橋治之の原点<2/2>
■ジェニングス著『FIFA 腐敗の全内幕』の問題点
──ところでFIFAの不正に関しては、アンドリュー・ジェニンングスの『FIFA 腐敗の全内幕 』が、田崎さんの本に先駆けて出版されています。当然、お読みになったと思いますが、感想は?
田崎 うーん。ちゃんと取材しているところと、していないところの差が激しいなと思いました。日本に関する部分は、ほとんど首を傾げてしまいましたね。ジェニングスさんという人は、端的に言えば「タブロイド紙的な」ジャーナリスト。きちんと裏を取らずに断言してしまう傾向があるんですよね。もちろん、不正に対する怒りそのものは間違っていないんですけど。
──特に「これは違うぞ」っていうところはありましたか?
田崎 日本に関しては、電通の話なんかも含めて全部違う。取材する気もなかったと思いますよ。それこそイギリス人は、「サッカーは自分たちのものだ」と思っているし。彼がそこまでとは思わないけど、でもやっぱり日本で起こっていることには彼らは興味がないんですよね。取材する気もないし資料も集めてないから、思い込みで書かれてある。そういう意味では、非常に微妙な本だと僕は思います。
──逆にジェニングスさんの本から影響を受けた部分は?
田崎 ないですね。さっきも言ったように、ジェニングスさんは腐敗追及のために突き進む人だと思うんですよ。僕はちゃんとファクトを集めて検証してやるのでスタイルが違いますから。逆に、ああいうのも羨ましいなとは思います。あれはアングロ・サクソンにしかできない(笑)。
──そうですか(笑)。
田崎 日本人はシャイで遵法意識が強いので、告発が少ない。ジャーナリズムが成立しにくいという土壌があります。加えて、サッカー政治の中心は欧州。それだけで、向こうに住んでいるジャーナリストのほうが日本の僕らに比べて圧倒的に有利なんですよ。
だからこそ日本にいる僕らは、丁寧に調査しながら書くしかないし、彼らがちゃんと取材してこなかった「電通とFIFA」についての本を出版することにも意義が出てくる。そういう意味では、ジェニングスさんとかイギリスのジャーナリストが書いていることがすべてではない。日本人の書き手として、知らしめることが必要だと思った部分はあります。
──なるほど。ところでこの本の帯に「全員悪人」とありますけど、悪人たちは北中米と南米の人間ばっかりだったことに関しては、どうご覧になっています?
田崎 単に、やりやすかったということだと思います。ただ、あまりにも彼らのやり方がずさんだったわけで、それで摘発できたわけですよね。逆に、収賄する側のカタールの人間は誰も摘発されていない。そこはアメリカなりFBIなりの限界だったんでしょうね。
──今後、カタール側がどう関わっていたかについては暴かれるでしょうか?
田崎 わからないです。まあ、プラティニが全部知っているんじゃないんですかねぇ(笑)。僕がジェニングスさんの本がアンフェアだと思ったのは、カタールについて何も書いてないことなんですね。カタールとプラティニの付き合いとか、何も書いてないじゃないですか。あれはアンフェアだと思いますよ。そこにはたぶん、何らかのバイアスがかかっているとしか思えない。
──この本を書き終えて、ご自身の今までやってきた仕事の中での位置づけについては、どう捉えていますか?
田崎 電通とFIFAというワンテーマで書いたというのは、今までの僕の仕事ではあまりなかったスタイルですよね。電通にしてもFIFAにしても、とことん書こうと思ったら広がりすぎてしまうので、今回に関してはトリミングしたという感じです。
──トリミングというのは、非常に写真的な発想ですが、本書は絶妙なアングルから切り取っているという印象です。ちなみに高橋さんの感想は?
田崎 高橋さんは「まぁいいんじゃないの?」っていうのと、あとは「売れてんの?」って感じでしたね(笑)。