【ゆきラボ】読書会のご案内と、「読書感想文」のないドイツの小学校
こんにちは!今日のゆきラボでは、今週末に開催されるオンライン読書会と、少し広く「本の楽しみ方」というものについて、子どもたちを通じて感じたことをお届けできればと思います。
まずはさっそく告知から。
「本にはこう書かれているけど、実際のところ本当にできるの?」
「そうはいっても現実的に難しいところもあるよね?」
「ドイツではそうかもしれないけど、日本だと無理だよ」
本を読んで浮かんだ意見や疑問、思いを自由に交換できる場になれば幸いです。こちら、フッスバルラボの会員のみなさま限定の企画となっておりますので、参加をご希望の方で当Webマガジンを購読されていない方は、まずは会員としてご登録をよろしくお願いいたします!
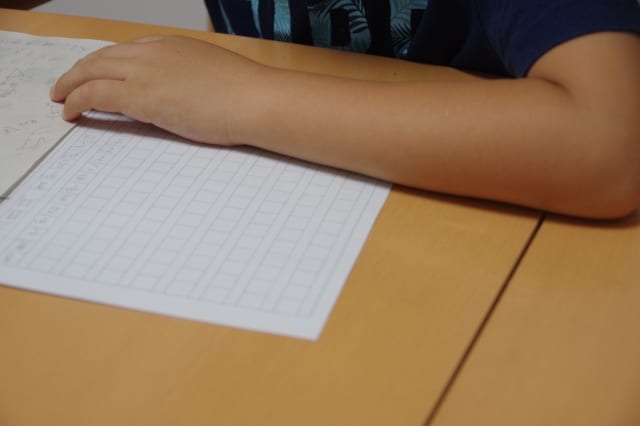
読んだものについて話す、あるいは意見や感想をまとめる、というと、私はなんとなく子どもの頃に書かされた読書感想文を思いうかべてしまいます。私は読書は寝食を忘れるくらい好きだったのですが、読書感想文は大嫌いだったので、余計にそんな連想をしてしまうのかもしれません。
そういえば、とふと気づいたのですが、ドイツの公立校に通う我が家の子どもたちが「読書感想文」なるものを書いていた記憶がありません。宿題として家でやっていないだけで、学校ではやっているのかな?と思って聞いてみると、2人とも「あ、そういえば日本みたいな読書感想文は小学校ではやってないなあ」とのこと。
(ちなみに2人とも日本語教室に通っていたので、そこでは日本式の「読書感想文」を書くという経験もしています)

では何をやるのか?2人とも小学校で経験したのは本の紹介(プレゼンテーション)でした。読んだ本がどのジャンルの本なのか、どんなあらすじの本で作者は誰なのか、いつ書かれた本なのかなどを読書カードにざっくり箇条書きにまとめて、それを元に、自分の好きな本を1冊クラスみんなの前でプレゼンしたり、自分の好きな場面を音読したりしたのだそうです。低学年の子どもにとっては、原稿用紙にきっちり「感想文」を書くよりもハードルが低くて楽しめそうですね。
ギムナジウム(小学校高学年・中・高の一貫校)に進学した長男は、その後、学校で何度か本について文章で自分の意見をまとめたり、プレゼンテーションをするということも経験していますが、長男いわく「読んだ本について、文章にきちんとまとめることも大事だけど、それよりもメインなのは、みんなに本のことをどう伝えるかのほう」なのだそうです。
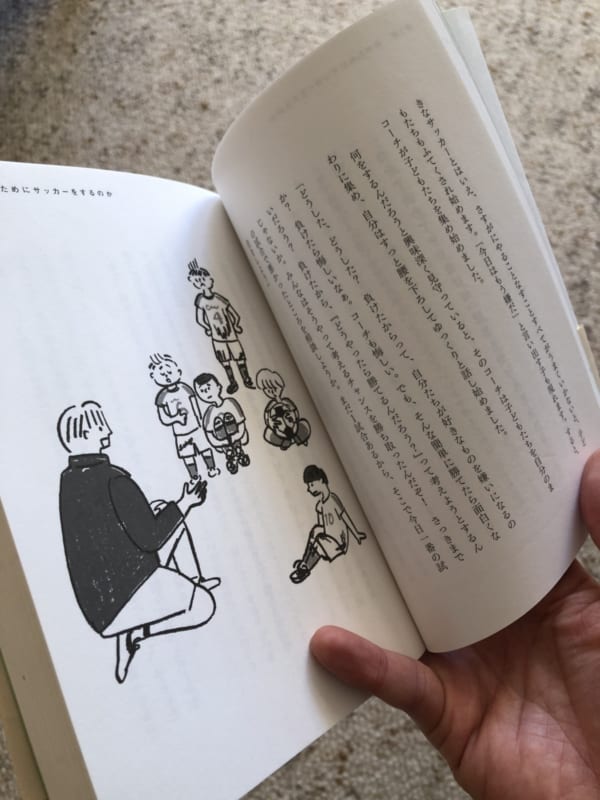
おそらく、ここでWebマガジンをお読みくださっている方は、新聞や雑誌や本などの文字メディアが好きな方、読むということを日常的に楽しんでいらっしゃる方が少なくないのではないかと思います。この読む楽しさにもバリエーションがたくさんあって、読むだけでなくSNSなどで自分なりの視点を発信する楽しさ、他の方と意見交換する楽しさ、読み物が書かれた背景について深掘りする楽しさ、そして読んだものを1人で、あるいはごく親しい間柄で、ゆっくり反芻する楽しさ、いろいろな楽しみかたがあるはずです。
初の試みである今回の読書会では、ぜひ、そうした様々な「読む」という楽しさを味わって頂ける場にもなると良いなと思っています。たくさんのご参加、お待ちしております!
来週の「ゆきラボ」もどうぞよろしくお願い致します。

