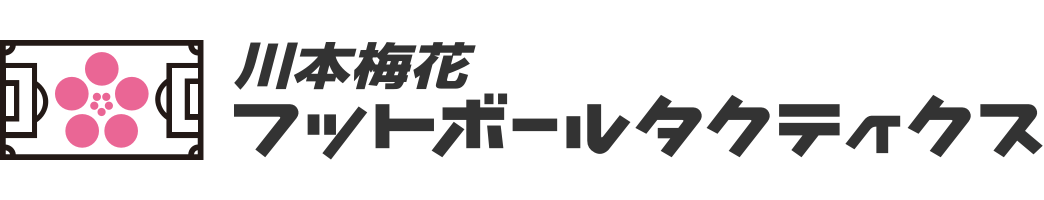【試合分析】イエローゾーンを制した八戸が勝者に J3第25節 #いわてグルージャ盛岡 0◯2 #ヴァンラーレ八戸 @vanraure @grulla_staff
イエローゾーンを制した八戸が勝者に
2019明治安田生命J3リーグ第25節
いわてグルージャ盛岡 0◯2 ヴァンラーレ八戸
https://www.jleague.jp/match/j3/2019/100507/live/
10月5日の土曜日、明治安田生命J3リーグ第25節、いわてグルージャ盛岡対ヴァンラーレ八戸の試合が北上総合運動公園北上陸上競技場で行われた。青森県のチームと岩手県のチームの戦いから「南部ダービー」と呼ばれる戦いは、2-0で八戸に軍配が上がる。
青森県には、南部藩(盛岡藩)と津軽藩(弘前藩)と斗南藩の3つの藩がある。今回の南部ダービーの「南部」とは、次の事柄から生まれた。明治4年7月に行われた行政改革の1つ、廃藩置県がなされる前、南部藩の管轄だった地域は、青森県東部から岩手県中部だった。八戸藩と七戸藩(現盛岡)の領主の名前が南部氏だったので、これらの地域を南部と呼ぶようになった。津軽藩は現在の弘前市にいた津軽氏が領主だったので、そのまま津軽藩となった。しかし、斗南藩はそうした事情と異なっている。青森県下北地方に移住させられた会津藩士たちが住んでいた地域を、斗南藩と言っていた。それは廃藩置県が行われる前までの名称だった。津軽藩、南部藩、斗南藩という名前は、廃藩置県の施行と同時に消えうせてしまう。
実は、筆者の先祖は、会津藩士で性を服部と呼んでいた。服部は、戦国時代から活躍した服部半蔵の一族だったという。服部は、明治政府から下北地方に追いやられて、田名部という地域に足を踏み入れる。やがて、筆者が生まれた風間浦村一帯の土地を保有して、地域の管轄人になり、その地で寺子屋を初めて開いて識字意識の発達に貢献した。要するに、武士だった先祖が、地域の農民や漁民に読み書きを教えたということである。
子供のころ、筆者は母親に「この地域の土地は昔、全部ウチのもんだったんだよ」と言われたことがあった。それで、自分の先祖がどんな人だったのかが気になって調べたことがある。会津から下北に移住した先祖・服部の子供(2世)が、「飲む打つ買う」に溺れて、特に大酒飲みだったので、借金の肩代わりとして所有していた一帯の土地を売り払ってしまった。それで、先祖の服部の孫(3世)が酒飲みを嫌い、彼の一人娘の養子に求めた条件が、「酒を飲めない人」だったそうである。
筆者は、子供のころから「お前は会津藩士の服部の一族だから、やればできる」と学校の先生に言われたものだった。昭和ってそういう時代なのである。
ローカルな話はこれくらいにして、試合のポイントに移ろう。
以下が両チームのシステムを組み合わせた図である。

岩手の「3-4-2-1」に対して八戸も「3-4-2-1」のミラーゲームになった。同じシステム同士の戦いは、両チームが何もしなければ、対面するそれぞれの選手がマッチアップ状態になる。そこで注目するべき点は、いかにしてマッチアップ状態を回避するのかである。つまり、「ズレ」をいかにして意図的に作っていくのかにある。ポジションで言えば、両ウイングバック(WB)と1トップの下にいる2シャドーの働きが重要になってくる。
■イエローゾーンに気を付けろ!
イエローゾーンとは、ゴールライン付近を指す言葉である。両チームともに、イエローゾーンにいかにボールを運んで攻略するのかに力を注いでいた。岩手は、ウイングバックの太田賢吾をこのゾーンに走らせて攻略している。

このシーンは、太田がタッチラインに始めから張っていた。WB佐藤和樹のポジションがピッチの中よりだったので、太田がフリーでボールに触れることができた。前を向いてドリブルでイエローゾーン目掛けて侵入する。佐藤は太田を後追いするが追いつけない。相当に危険なシーンになってしまった。この場合、理にかなった対処は、次のようになろう。左ストッパーの須藤貴郁が最初に太田に寄せられないと危険度は増してしまう。実際に、別なシーンでは、太田のイエローゾーンへの進行を事前に察知した須藤は、素早く体を寄せていた。須藤が寄せられれば、佐藤や差波優人も降りてきてケアができる。最悪でも、クロスを上げられずにCKに逃れられる。
3バックの場合、どうしても弱点となるのは、攻撃参加したWBの“裏のスペース”である。高い位置を取ったWBは、すぐにファーストポジションに戻れない。したがって、WBの背後の場所であるイエローゾーンが最大の攻略の場所となるのだ。

PKを決めた須藤が、大きな一本のパスを逆サイドに通した場面があった。右WBの國分将にボールが渡って、ドリブルしながらイエローゾーンに入って行った。そこからグラウンダーのマイナスのクロスをセンターバック(CB)とGKの間に入れる。

追加点となった谷尾昂也のゴールは、こうしたサイドからの繰り返された攻撃によって生まれた。ワイドなポジションを取ってサイドから攻めれば、相手もワイドにポジショニングをして守備に当たる。そうすると、中央に人数を掛けられないので薄くなってくる。相手の目がサイドに追いやられるので、中央の裏を狙った縦パスが有効となる。國分から中央にいる谷尾へとパスが出された時、岩手のCB2人の間で谷尾が1人浮いた状態でボールを受けることができた。したがって、谷尾はボールを受けながら、CB1人と対面できたのだ。この1人をかわせば、GKと1対1の局面を作れる。実際に谷尾は、GKと1対1になってシュートを決めた。
試合のポイント
サイド攻撃を行ってイエローゾーンに侵入した選手が、グラウンダーでCBとGKの間にマイナス方向のパスを出した。
サイド攻撃を意識させることで、中央のケアが薄くなる。その結果、中央への縦パスや相手のCBの裏を狙うパスが有効になった。
こうした攻撃に執着を持って何度も繰り返した八戸が「南部ダービー」を制したのである。
川本梅花