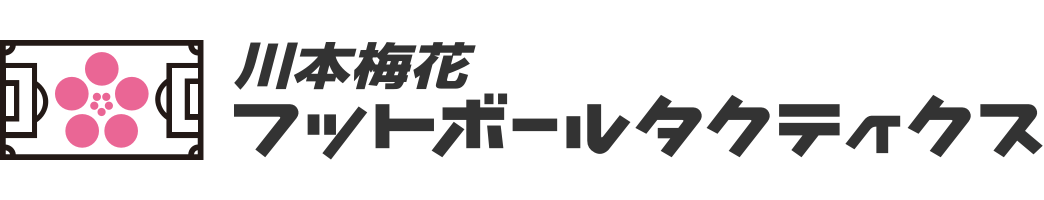【試合分析】#清水慎太郎 ストライカーの真髄を見せる J2第3節 #水戸ホーリーホック 1〇0 #V・ファーレン長崎 #mitohollyhock
■カウンターサッカーの条件
カウンターサッカーを戦術として取り入れるならば、それには2つのやり方がある。
(1)自陣内に思いっきり相手を引き込んでカウンターをする。
(2)相手陣内の高い位置でボールを奪って、ショートカウンターをする。
引いて守るチームが採る戦術を「カウンターサッカー」と捉えるのは間違っている。また、ロングボールを多用するからカウンターであるというのも正しくない。では、カウンターサッカーとは何か。それは、いかに早く相手のゴールまでボールを運ぶか。そこがポイントとなる。意図的に相手を自陣に引き込み、意図的にボールを奪ってすばやく攻めるという姿勢がなければ、カウンターとは呼ばない。
相手からボールを奪う場合、前を向いてボールを奪うという姿勢が肝心となる。そのため、相手を自陣内のある一定の場所に引き込んでからボールを奪う必要がある。
実は、このようなカウンターサッカーは、長崎の得意とする攻撃戦術で、手倉森監督の好みのやり方である。前半、水戸がボールを支配して、長崎の陣地でボールを動かす場面が多々あったのは、長崎が意図してボールを回させていたからである。
長崎からすれば、ボールを奪ったら一気にカウンター攻撃に転じようと考えていた。しかし、ボールを奪われた水戸は、前線の選手がボールをGKまで寄せているため、長崎はなかなかカウンター攻撃に入れなかった。
つまり、水戸の前線の選手がGKまでボールを追いかけることで、長崎のカウンター攻撃を防いでいたのだ。これは、長谷部茂利監督の指示だったと思われる。なぜなら、この3試合を見ていて、前線の選手が、ボールを追う時と追わない時が、試合の状況によって意図的に振り分けられているからである。
筆者にとって、いくつかの想定外があった。両チームとも同じシステムになるが、水戸は、ボールがあるサイドから逆のサイドに大きくボールを振って、相手選手のスライドのズレを使ってくると想定していた。しかし、大きなチェンジサイドを使ってきたのは、水戸ではなく長崎の方だった。右サイドにいたセンターハーフ(CH)の黒木聖仁から左サイドバック(SB)の亀川諒史に何度か大きなパスが送られている。
水戸が採用したのは、中から外にボールを追い出して奪うやり方。つまり、サイドラインにボールを追い込んで奪う守備戦術だった。
ボールがサイドにあったら、そこでボールを奪う。ボールが中央にあったらサイドに追いやらず、ボールの前に立ってブロックを作り防御する。サイドは2対1の数的優位で対応。中央では1対1になってディレイする。水戸は、長崎の選手が以下のエリアに入り込んでいたら、ボールにアタックしていた。