ツンさんが唱える「ちょんまげイズム」とは何か? 震災から8年、持続可能な支援を考える<2/2>

■「ボランティアの壁」を乗り越えた瞬間とは?
──間もなく東日本大震災から8年になります。その間、ちょんまげ隊の活動もずっと続いているわけですが、今ではツンさんがなぜ被災地支援活動を続けているのか、若い世代の中にはご存じない人も少なくないように感じています。とはいえツンさんは「もともとボランティアをするようなタイプの人間ではなかった」と、ご自身でも明言していますよね。
ツン おっしゃるとおりです。ずっとボランティアというものに対して、壁みたいなものを感じていました。それには理由があって、95年に阪神淡路大震災があった時に、僕の奥さんのお姉さんが被災しているんです。(神戸市)長田区のすぐ近くに住んでいて、何日か経ってようやく連絡がとれたんですけど「支援物資を持っていきます!」って言ったら断られたんですね。その時に「ああ、素人は行ったらいけないんだ」と思ってしまって。
──なるほど、それが「ボランティアへの壁」として、ずっと残っていたと。
ツン そうですね。ボランティアをやっている人が嘘くさく見えてしまって。自分が知らない世界に対して、人間はどうしても批判的というか懐疑的になってしまいますよね。そういう経験があったからからこそ、今はボランティアの敷居を下げたいとずっと思っています。感覚としては、ボランティアに参加するのとアウエーでサッカーの応援に行くのは一緒なんですよ。
応援もボランティアも、絶対に必要なものではないし、自己満足の世界かもしれない。それでも、さまざまな人たちが同じ目的のために一丸となるのは一緒なんですね。僕らも被災地の人たちが喜んでくれたり、子供たちの笑顔に接したりすると、それだけで嬉しいし感動もある。ちょっとしたきっかけがあれば、誰でも東北や熊本に行けるんですよね。そして大事なのは「楽しんでやる」ということ。僕自身、楽しめたからこそ、8年も続いたんだと思っています。
──そんなツンさんが「ボランティアの壁」を乗り越えられたのは、何がきっかけだったんでしょうか?
ツン ご存じのように僕の本業は靴屋です。あの震災ではウチのお店の窓ガラスが割れたし、僕自身も家族や従業員を守らなければならない立場にありました。そんな中、東北にはすべてを津波に流されて、靴さえもない被災者がいることをTVで知ったんです。「じゃあ、ウチの倉庫に残っている靴を持っていこう」と、シンプルにそれだけです。
──まさか、それから8年間も被災地と付き合うことになるとは夢にも思わず。
ツン もちろんです。「これから100回、東北に行きなさい」なんて言われたら、絶対に行かなかったですよ(笑)。偽善のつもりで避難所に靴を1回だけ届けたら、それで完結。最初はそんなふうに考えていました。
──ところがそうならなかったのは、ツンさんがちょんまげ姿で現地に赴いたからだと思うんですよ。結果として、あのちょんまげ姿が継続的なボランティアのシンボルとなっていくわけですが、そもそもなぜ、ちょんまげだったんでしょうか?
(残り 4564文字/全文: 5861文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。
会員の方は、ログインしてください。








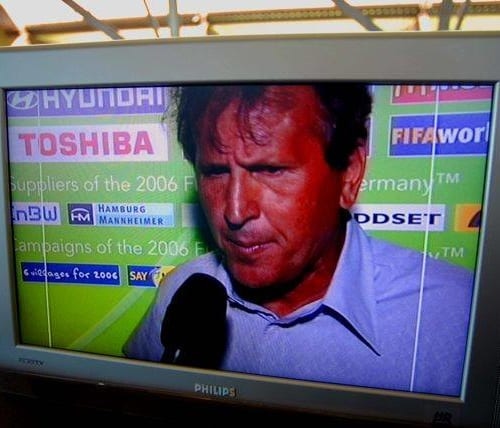




外部サービスアカウントでログイン
Twitterログイン機能終了のお知らせ
Facebookログイン機能終了のお知らせ