日本人アスリートはなぜ「団体闘争」が苦手なのか? 河内一馬と考える『芸術としてのサッカー論』<2/2>
■すぐに怒る欧米人と感情表現が苦手な日本人
──ここまでの理論の展開は非常に興味深いですね。これまでにも「日本人はなぜサッカーに向いていないのか?」という議論になったときに、やれ「欧州と比べて歴史がないから」とか、やれ「日本人は農耕民族だから」といった抽象的な議論ばかりだったように思います。ところが河内さんはサッカーに限定せず、まずスポーツをいくつか分類した上で「日本人はなぜ『団体闘争』が苦手なのか」という問題提起をしたところに新しさを感じます。それにしてもなぜ、こうした発想に至ったのでしょうか?
河内 もともと「日本人というのはどういう民族なんだろう」とか「どういう特徴があるんだろう」ということを勉強するのが好きだったんです。一方で「団体闘争」というのは、ものすごく文化的な依存度が強いと思っていて、国によってはものすごく特徴が出る。たとえばチームワークひとつをとっても、「競争型のチームワーク」と「闘争型のチームワーク」の2種類があると考えています。
──「競争型」はチームメイトに干渉しないチームワーク、「闘争型」は逆にぶつかり合うことをいとわないチームワーク、ということでしょうか?
河内 そのとおりです。前者の典型例がまさに日本人で、基本的に自分が納得しなくても前に進めることができるし、周囲が心地よくなるための努力さえできる。でもサッカーの場合、合わない部分があったら、ぶつかってでもそれを解決しないとチームとして機能しないですよね? そこは欧米人のほうが、はるかに得意だというのが僕の考えです。
──よくわかります(笑)。ただし「競争型のチームワーク」と「闘争型のチームワーク」というのは、決して優劣をつけられるものではないようにも思うのですが。
河内 もちろんです。どっちがいいとか悪いとかではなく、やっぱり日本人が築こうとするチームワークというのは「団体闘争」には合わないという話です。だったら「団体闘争」を前提としたチームワークを築いていくしかない。そもそもチームメイトと意見が対立するのは、日本人も欧米人も関係なく起こり得るものですが、ぶつかりながらすり合わせようとするのが欧米人で、不満を飲み込んで周囲に配慮するのが日本人。なぜそうなるのかというと、日本人は感情表現が苦手だからだと思っています。
(残り 4623文字/全文: 5631文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。
会員の方は、ログインしてください。






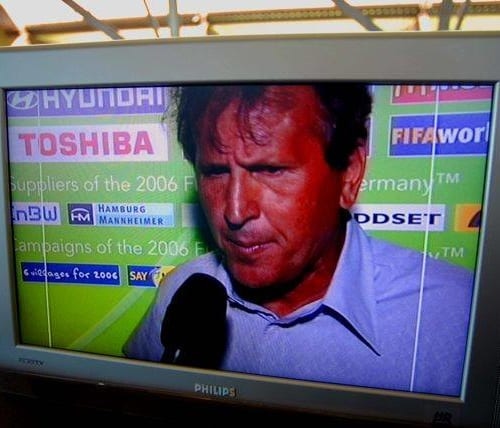





外部サービスアカウントでログイン
Twitterログイン機能終了のお知らせ
Facebookログイン機能終了のお知らせ