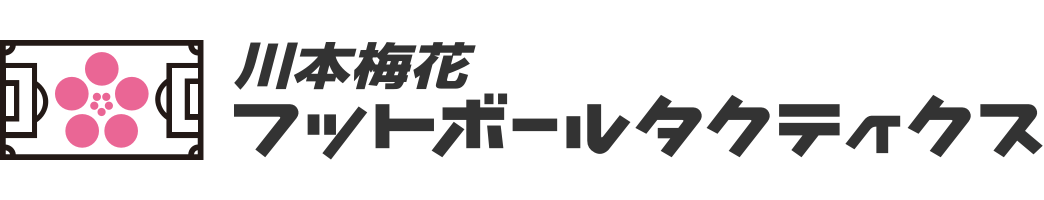【試合分析】#清水慎太郎 ストライカーの真髄を見せる J2第3節 #水戸ホーリーホック 1〇0 #V・ファーレン長崎 #mitohollyhock
■「能動的な守備戦術」の水戸と「受動的な守備戦術」の長崎
水戸と長崎の守備戦術を文法用語に照らし合わせれば、水戸は「能動的な守備戦術」、長崎は「受動的な守備戦術」と言える。「能動的」とは「自分たちから仕掛ける」という意味だ。また「受動的」とは「自分たちから仕掛けない」という意味になる。
両チームの大きな違いは、前線の選手がどこまでボールを追いかけるのかにある。水戸は長崎のGKまでボールを追いかけるが、長崎は水戸のセンターバック(CB)までしかプレスに行かない。
水戸の狙いは、前線の選手が相手GKまでボールを追うことで、相手のビルドアップをやりづらくすることにある。さらに前線の選手がボールを奪えたら、一気にショートカウンターに転じられる。
長崎は、CBまでしかボールを追わないので、相手にビルドアップのチャンスを与える。そうすることで、相手にボールを持たせて一定の場所に誘い込む。そこでボールを奪ったら一気にカウンターを仕掛ける。
長崎が55分になって、長身の長谷川悠を投入したのは、負けているからロングボールを放り込む作戦ではなく、長谷川をターゲットマンにして、あくまでカウンター戦術を取ろうとしたからだろう。さらに、セットプレーでの得点を期待しての起用と考えられる。
勝利のポイント
黒川・前・茂木・清水の連動性が、清水の決勝点をもたらした。
奪ったボールが清水に渡った瞬間、前線にいる3選手(黒川・前・茂木)がゴールに向かって一気に走りだす。その3選手がペナルティエリアに入ると、右側に動くことで長崎のDFを引っ張る。結果、中央にスペースが空き、そこに清水が入る。茂木からのパスを受け、清水はゴールを決める。
このようなプレーが生まれた背景には、長谷部監督が指導しているトレーニングがあり、その指導が間違っていなかったことの証明となる。トレーニングしていないことは、実戦で出せないからだ。次節・ジェフユナイテッド千葉戦では、どのような長谷部サッカーが披露されるのか、楽しみになってきた。
#川本梅花