【きちゼミ】自主性ってなんだ?自分の行いに自分で責任を担い、そのための準備に取り組むことができる性質

▼ 自主性ってなんだ?
先日開催したWEB講習会「『ドイツの子どもは審判なしでサッカーをする』から学ぶ 子どもたちが自主性を育むための7つの法則」ではタイトルにあるように自主性をテーマにいろんな角度からお話をさせていただいた。
そもそも自主性とはなにか?
講習会前にいろいろ調べてみたが、辞書を引いてみると「自主性とは他人からの指示や援助を受けることなく、自ら率先してやるべきことを行う態度や性質」と書かれている。
さら調べてみると「自主性のある子はやりたくない勉強でも『やらなければならない』と分かっているので、先生や親に言われなくても自分から取り組む。つまりやる気の有無や好き嫌いを超越するのが『自主性』」なんて表現をみつけた。
なんか違う…。
僕がイメージしている自主性ってそういうことじゃない。
ドイツ語で定義をいろいろと調べてみたら、こんなしっくりくる表現があった。
「自主性とは、自分で考え、自分で判断し、自分で決断し、自分で行動し、そのことに対して自分で責任を担い、そのための準備に取り組むことができる性質」
この「自分で責任を担い」というところってすごく大事だと思うのだ。やりたいことがある、やろうとしていることがある。だからそのための主張をする。でもする以上、「言って終わり」「やって終わり」ではなく、うまくいかなかったときの責任はちゃんととるし、そうならないために入念に準備をしていくことがセットになっていないとだめだと思うのだ。
ここを念頭に置いたうえで、では「そのために育成年代では何を、いつから、どのように取り組むべきか」が考えられないといけない。特に日本社会的に自主的な取り組みが身につきにくい環境にいるのであれば、よりそこへフォーカスしたアプローチを整理し行くことがすごく大事ではないだろうか。
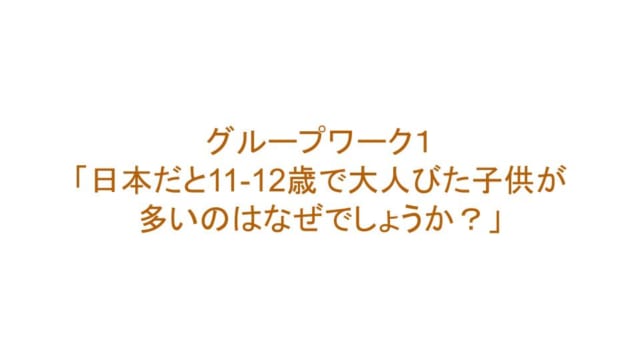
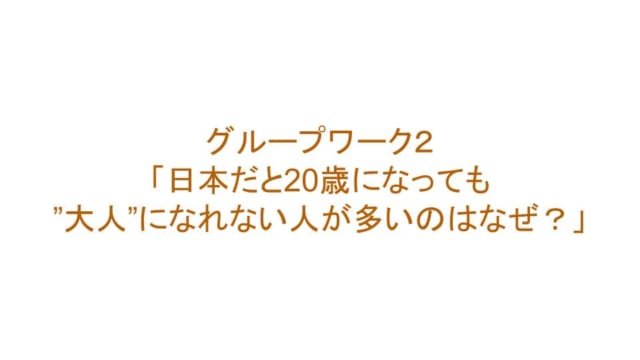
▼ 大人みたいな子供になるのは早いのに、いくつになっても大人になれない人が多いのはなぜだ?
個人的な印象になるのかもしれない。でも同年代の子どもたちと比べて、日本の11-12歳は明らかに大人びている子が多い。違う言い方をするとさめている。はしゃいだりしない。感情を表に出さない。
一方で20歳ぐらいの年代を比較すると、自分の言葉で語り、自分の足で歩き、自分の目で見て行動する人が多いドイツと比べ、目標もあいまいなまま毎日を過ごしていている大学生が日本には相当数いる。
僕が思うに大人びた子供が多いのは、小さいころからの刺激が多すぎるから。あれもこれもと与えられ続けていたら、だれだってすぐに満腹になってしまう。感覚がマヒしてきてしまう。
さらに忙しすぎる。毎日スケジュールでいっぱいだ。一つ一つに反応していたら体も頭も心も持たない。だから自分でガードする。反応しないようにして自分を守る。
そして大人からの圧力だ。大人が「いい子」だけを求めすぎているので、子どもたちはそういう自分を演じざるを得ない。それ以外の自分だと認めてもらえないんだからしょうがない。でもそういう環境にいる時間が長くなればなるほど、いつまでも本当の自分らしさというものには気づけない。自分が何が好きで、何をやりたいのかとも向き合えない。
失敗することは許されずに、とにかく大人が引いたレールの上を、大人が求める姿形と歩き方でたどっていくのが多くの日本の子どもたちが向き合っている現実だ。そりゃ自主性なんて育まれない。
このままでいいのか。
ダメならどうしたらいいのか。
いつか誰かが何とかしてくれるのを待つしかないのか。
次ページでは講習会の際に行ったグループワークでやり取りをした内容をご紹介したいと思う。考えるうえでの一助になったらうれしい限りだ。
(残り 2492文字/全文: 4047文字)
この記事の続きは会員限定です。入会をご検討の方は「ウェブマガジンのご案内」をクリックして内容をご確認ください。
ユーザー登録と購読手続が完了するとお読みいただけます。
会員の方は、ログインしてください。





外部サービスアカウントでログイン
Twitterログイン機能終了のお知らせ
Facebookログイン機能終了のお知らせ